競馬の予想の仕方が分からず、立ち止まってしまってはいませんか。競馬予想で何を見るべきか、また競馬予想で何を重視するべきかという問いは、競馬を始めたばかりの方が最初に直面する大きな悩みです。この「予想の軸」が定まらないままでは、レースが近づくたびに情報収集に追われてしまいます。
例えば、体系的な知識を求めて競馬の予想の仕方に関する本を手に取ってみても、理論が先行して実践に結びつかないと感じるかもしれません。あるいは、手軽さを重視して競馬 勉強アプリを活用しようとしても、データが断片的で何をどう分析すればよいか迷ってしまうこともあります。もっと手軽な情報源として、Yahoo!知恵袋で他の人の競馬予想方法について質問したり、匿名掲掲示板の2ch(現5ch)で競馬の予想の仕方に関する本音の情報を探したりする方もいるでしょう。
しかし、どの情報源にも一長一短があります。本は体系的ですが情報の鮮度に欠ける場合があり、アプリは速報性に優れますが情報が断片的になりがちです。さらに、知恵袋や2ch(5ch)といった情報源は、利用者の本音が垣間見える一方で、情報の信憑性は担保されていません。このように情報が溢れすぎているために、「結局、おすすめの競馬予想方法はどれなのか」「本当に当たる人の競馬予想における着眼点は、自分とどこが違うのか」と、かえって混乱してしまうことも少なくないのです。
この記事では、そうした情報の洪水の中で「予想の羅針盤」を求めている方へ向けて、数ある競馬予想の重要ファクター(馬場、能力、騎手、展開など)を分かりやすく整理します。初心者から一歩進んで「当てる予想」を目指すために必要な、競馬の予想の仕方の基本的な考え方から、多様な情報源の適切な活用法までを分かりやすく解説します。
- 競馬予想で見るべき基本的な順序
- 馬場状態や馬の能力を分析するコツ
- 騎手や展開読みの重要性
- 多様な情報源の活用方法と注意点
基本から学ぶ競馬の予想の仕方
競馬予想には、血統、調教、データ、パドックなど、実に多様なアプローチが存在します。しかし、どの手法を取り入れるにせよ、まずはレースの勝敗を左右する「基本の型」を理解することが、予想精度を上げるための最短ルートです。ここでは、予想を組み立てる上での基本的な順序や、重視すべきファクターについて掘り下げていきます。
- 競馬予想ではまず何を見るべきか
- 競馬予想で何を重視するべきか
- 勝敗を分ける競馬予想の重要ファクター
- 当てる人の競馬予想における着眼点
- 初心者におすすめの競馬予想方法
競馬予想ではまず何を見るべきか
- YUKINOSUKE
競馬予想を何から始めればよいか迷った場合、多くの人がまず出走馬の過去の成績が一覧になった「馬柱(うまばしら)」に目を向けがちです。どの馬が前走で勝ったのか、どの馬が人気なのかは、非常に分かりやすい指標と言えます。
しかし、より本質的で精度の高い予想を行うためには、まず「馬場」の状態を確認することから始めるのが基本中の基本となります。出走馬という「役者」に注目する前に、彼らが走る「舞台」のコンディションを把握することが先決です。
なぜなら、馬が走るコース(競馬場)という「舞台」の状態が、その日のレース傾向、つまり「どのような馬が好走しやすいか」を決定づける最大の要因だからです。馬の能力という「ソフト」がどれだけ優秀でも、それを発揮する「ハード」である馬場が合っていなければ、本来の力は出せません。
例えば、芝がよく乾いて硬くなった「カチカチの高速馬場」であれば、絶対的なスピードや瞬発力が求められます。逆に、雨が降り続いた「田んぼのような荒れ馬場」であれば、スピードは出にくくなり、馬力(パワー)やスタミナがなければ上位には来られません。このように、求められる能力が全く異なるのです。
実践的な「馬場読み」のヒント
馬場状態を把握するには、JRAが公式に発表する「良・稍重・重・不良」という情報だけでは不十分です。以下の点を組み合わせて判断することが推奨されます。
- JRA公式データの確認:JRA公式サイトの「馬場情報」で公開される「クッション値(芝の硬さ)」や「含水率(馬場に含まれる水分量)」の数値を確認します。
- 当日のレースタイム:予想するレースの前に、同じコースで行われたレースの「走破時計」を見ます。平均的な時計より速いのか、遅いのかは最大のヒントです。
- VTR(パトロールビデオ)の確認:当日のレース映像で、「騎手たちが馬場のどのあたりを通っているか(トラックバイアス)」を確認します。もし全騎手が内側(ラチ沿い)を避けて外側を回っているのであれば、内側の芝が荒れて走りにくいと判断できます。
- 芝の色やキックバック:「芝の色」が部分的に濃くなっている(傷んでいる)箇所や、馬が走った際に芝や土砂(キックバック)がどれくらい飛び散っているかでも、馬場の状態を推測できます。
競馬予想の基本的な順序としては、以下の流れを意識すると、思考が整理されてスムーズに進みます。
競馬予想の基本的な順序
- 馬場読み:当日の馬場状態(時計、走りやすさ、有利なコース取り)を把握する。
- 馬の能力分析:その馬場に適性がありそうな馬はどれか、出走馬の能力を分析する。
- 騎手の性質分析:選んだ馬を、騎手がうまく導けるか(戦法や馬との相性)を考える。
- 展開読み:レースの流れ(ペース)が、その馬と騎手に向くかを予測する。
この順序が全てではありませんが、特に初心者のうちは「①馬場→②馬→③騎手→④展開」という思考の連鎖を意識するのがおすすめです。この4つの要素は独立しているのではなく、密接に関連し合っています。
効率的な進め方としては、週中に馬の能力分析(②)という時間のかかる作業を済ませておき、レース当日に馬場読み(①)を行ってから、最終的な判断(③、④)を下すのが、最も現実的で精度の高い方法と言えるでしょう。
まずは競馬場という「舞台」の特性を当日のレースから読み解くこと。これが、単なる「当てずっぽう」から脱却し、論理的な予想を組み立てるための精確な第一歩となります。
競馬予想で何を重視するべきか
- YUKINOSUKE
競馬予想において最も重視すべきなのは、「その日の馬場の特徴」と「出走馬の能力(適性)」がどれだけ精密にマッチしているか、という点です。馬の能力を絶対的なものさしで測るのではなく、走る舞台(馬場)との相性という相対的なものさしで測る視点が不可欠になります。
「競馬予想の7割は馬場読みだ」という専門家の言葉があるほど、馬場はレース結果に直結する重要な要素です。どれほど優れた能力を持つスターホースであっても、その日の馬場状態(例えば、極端な道悪やカチカチの高速馬場)に適性がなければ、本来の力を発揮できずに敗れることは競馬では日常茶飯事と言えます。なぜなら、馬場は「そのレースで求められる能力」そのものを規定するからです。
具体例をいくつか挙げます。
- 例1:高速馬場
芝がよく刈り込まれ、乾燥して硬くなった状態です。この馬場では、絶対的なスピード(楽に前についていける基礎スピードや、直線での最高速度)が求められます。過去の持ち時計が速い馬や、地面を滑るような大きなストライド走法の馬が、その能力を発揮しやすい舞台です。
- 例2:荒れ馬場(パワー馬場)
連日の雨で時計がかかる状態や、開催が進んで芝が剥がれてしまった状態を指します。この馬場では、スピードよりも馬力(パワー)や、苦しくなってからの粘り強さ(スタミナ、乳酸抵抗力)が求められます。地面を力強く叩きつけるようなピッチ走法の馬が、パワーを要する馬場を得意とする傾向があります。
- 例3:摩擦の強い馬場
例えば、芝が長く伸びている(特に洋芝が使われる札幌・函館競馬場など)、または芝の密度が非常に高い状態です。この馬場では、スピードが削がれやすくなります。そのため、瞬発力(ギアチェンジ)だけで勝負するタイプは苦しく、長く良い脚を使える「ロンスパ力」や、摩擦に負けない「パワー」が求められるようになります。
ただし、この馬場読みには、表面的な情報に惑わされないための注意点が存在します。
注意点1:JRAの公式発表は「目安」でしかない
JRAが発表する馬場状態(良・稍重・重・不良)は、あくまで馬場に含まれる水分量などに基づいた目安です。同じ「良馬場」でも、芝の長さ、路盤の硬さ(クッション値)、JRAによるエアレーション(芝に空気穴を開ける作業)やシャタリング(路盤をほぐす作業)の有無、さらには開幕週か最終週かによって、性質は全く異なります。
「時計の出やすい良馬場」もあれば、「時計のかかる(力のいる)良馬場」も存在します。見るべきは公式発表の文字列だけでなく、実際の時計や、馬場の「摩擦」「グリップ」といった本質的な要素です。
注意点2:レース結果の「現象」と馬場の「本質」を混同しない
当日のレースを見て「差しが決まったから差し馬場だ」「外を回った馬が来たから外が有利だ」と短絡的に判断するのは危険です。
「差しが決まった」のは、本当に馬場のせいで差しが有利だったのでしょうか。それとも、単にそのレースが「ハイペースで前の馬が潰れただけ(展開の綾)」だった可能性はないでしょうか。逆に「前が残った」のも、馬場が前有利だったのか、単なる「スローペースで展開が向いただけ」なのかを区別しなくてはなりません。
短絡的な判断は、次のレースで全く逆の結果(展開次第で前残りになるなど)を招き、予想を混乱させる最大の原因になります。
馬の能力を「A馬はB馬より強い」と個別に評価する前に、まずは「その馬の能力(得意な走り方)を最大限に発揮できる舞台が、今日の馬場か」を見極めること。この「舞台と役者のマッチング」の精度こそが、競馬予想の精度を格段に上げる上で最も重要です。
勝敗を分ける競馬予想の重要ファクター
- YUKINOSUKE
前述の通り、馬場(舞台)と馬の能力(役者)がレースの根幹をなすことは間違いありません。この2つのマッチングを見極めるだけでも、予想の精度は大きく向上するはずです。しかし、どれだけ素晴らしい舞台が整い、優れた役者がいたとしても、その役者の能力を100%引き出す「騎手」の采配や、レース全体の流れである「展開」がかみ合わなければ、思わぬ取りこぼしや、逆に格下の馬による逆転が起こり得ます。
競馬予想とは、これら複数のファクター(要因)が複雑に絡み合うパズルを解く作業です。ここでは、予想を構成する各ファクターをもう少し深く掘り下げて解説します。
馬場読みの3大要素
前項で「馬場読み」の重要性に触れましたが、馬場を分析する上で重要な概念は「時計」「摩擦」「グリップ」の3つです。この3つの要素は独立しているのではなく、互いに影響し合っており、そのバランスでその日の馬場の総合的な特性が決まります。
①時計(どれだけ速いタイムが出やすいか)
これは馬場の「硬さ」や「走りやすさ」を示す最も分かりやすい指標です。同じ競馬場・同じ距離・同じクラスの過去のレースタイムと比較して、「平均より速い(高速馬場)」のか「平均より遅い(時計のかかる馬場)」のかを判断します。高速馬場ならスピード能力が、時計がかかる馬場ならパワーやスタミナが求められやすくなります。
②摩擦(スピードの維持しにくさ)
これは、馬がスピードを維持するのを妨げる抵抗力のことです。例えば、芝が長く伸びていたり、密度が濃かったり(特に洋芝)、馬場が柔らかかったりすると、馬の脚が芝や地面に取られて摩擦が強くなります。摩擦が強い馬場では、スピードを維持するためにより多くのパワーやスタミナが求められます。JRAが発表する「クッション値」(芝の硬さの指標)も参考になりますが、芝の生え方(密度や長さ)によって測定値が実態と異なる場合があるため、あくまで参考程度と捉える見方もあります。
③グリップ(地面を掴む力)
これは馬の脚(蹄)が地面をしっかりと掴む「引っ掛かり」の良さを指します。グリップが効く馬場では、馬は力をロスなく地面に伝えることができ、特に加速時(ギアチェンジ)にその差が出ます。一般的に芝が綺麗に生え揃っているとグリップしやすいですが、逆に芝が長すぎたり高密度すぎたりすると、今度は「摩擦」が強くなりすぎるという現象も起きます。ダートコースでは、砂の粒子の大きさや含水率(湿り気)が、このグリップと摩擦に大きく影響します。
馬の能力分析(6つの要素)
馬場(舞台)がどのような能力を求めているかを理解したら、次に出走馬(役者)がその能力を持っているかを分析します。馬の能力は多岐にわたりますが、主に以下の6つに分類して考えると、その馬の得意・不得意が整理しやすくなります。
| 能力 | 概要と注目ポイント |
|---|---|
| ①基礎スピード | 楽に追走できるペースの速さ(巡航速度)です。この能力が高いと、速い流れ(ハイペース)のレースでもバテずに追走できます。高速馬場では特に重要視されます。 |
| ②最高速度 | 追い出してからのスピードの最大値(トップスピード)を指します。いわゆる「末脚のキレ」や「瞬発力」と呼ばれる能力の源泉です。スローペースからの瞬発力勝負では、この能力が勝敗を分けます。 |
| ③乳酸抵抗力 | 苦しくなってから(無酸素運動状態)の粘り強さ、バテにくさです。ハイペースでの消耗戦や、摩擦の強い馬場での我慢比べになった際に求められます。 |
| ④ロンスパ力(ロングスパート力) | 長く良い末脚を維持する力です。「一瞬のキレ(最高速度)」はないものの、「長くいい脚を使う」タイプの馬が持つ能力です。早めに仕掛けるレースや、摩擦の強い馬場で優位に立てます。 |
| ⑤ギアチェンジ | トップスピードに到達するまでの加速力、いわば「0→100」の速さです。スローペースからの「ヨーイドン」といった瞬発力勝負や、直線の短いコース(中山や内回り)で特に問われます。 |
| ⑥パワー | 摩擦の強い馬場(重馬場やダート)や、中山競馬場のような急坂を苦にしない力です。この能力がないと、坂で失速したり、力のいる馬場でスピードを維持したりすることができません。 |
もちろん、一頭の馬がこれら全てを高いレベルで兼ね備えていることは稀です。大切なのは、前述の「馬場読み」によって、そのレースの条件(馬場、距離、展開)でどの能力が最も強く問われるかを予測し、その能力に長けた馬を見つけ出すことです。この「求められる能力」と「馬の持つ能力」が合致するかを見極める作業が、予想の核心となります。
騎手と展開
馬場と馬の能力を分析したら、最後の仕上げとして「その能力を騎手が引き出せるか」そして「レース展開がその馬に向くか」を考えます。これら二つは、レースの「不確定要素」でありながら、勝敗を左右する重要なファクターです。
騎手の性質分析
馬の能力を120%引き出す騎手もいれば、馬の癖や特徴を掴めず80%しか出せない騎手もいます。重要なのは「上手い・下手」という漠然とした評価ではなく、「馬の能力」と「騎手の得意な戦法」の相性です。
例えば、末脚(最高速度)が最大の武器である馬に、無理に先行させる戦法を得意とする騎手が乗ると、馬の長所を活かせずに終わる可能性があります。逆に、粘り強さ(乳酸抵抗力)が持ち味の馬に、後方で脚を溜める戦法を得意とする騎手が乗ると、持ち味のスタミナを発揮する前にレースが終わってしまうかもしれません。馬と騎手の「手が合う」かどうかを考える必要があります。
レース展開読み
レース展開、すなわち「ペース(レース全体の流れ)」も極めて重要です。ペースは主に「逃げ馬」の数や性質によって決まります。
- スローペースになりやすい条件:逃げたい馬が1頭しかいない場合。その馬が楽なペースで逃げられるため、スタミナを温存でき、前の馬(逃げ・先行)が有利になりやすいです。
- ハイペースになりやすい条件:逃げたい馬が複数いる場合。先頭争いが激しくなって全体のペースが上がり、前の馬はスタミナを消耗します。結果として、後方で脚を溜めていた馬(差し・追込)が有利になりやすいです。
どの馬が逃げて、どの馬が番手(2番手)につけるのか。そして、その2頭の騎手の性格(競り合うタイプか、引くタイプか)によって、ペースはある程度予測できます。この展開読みは運の要素も絡むため非常に難しいですが、予想の精度を上げるためには避けて通れないファクターとなります。
当てる人の競馬予想における着眼点
- YUKINOSUKE
競馬予想が上手い人、いわゆる「当てる人」は、競馬新聞に載っているレースの「結果(着順)」という数字だけを見ているわけではありません。もちろん結果は重要ですが、彼らが最も重視しているのは、その着順に至った「内容(プロセス)」です。
この「内容」を詳細に分析するために不可欠なのが、レースVTR、特にJRAが公式サイトで提供する「パトロールビデオ」の確認です。通常のレース中継は1着争いや人気馬を中心に映すため、後方や馬群の中で何が起きていたかは分かりにくいものです。しかし、パトロールビデオはスタートからゴールまで、全馬の動きを上空(斜め後ろ)から客観的に把握できるため、着順には表れない「真実」が隠されています。
当てる人は、この映像を繰り返し確認し、以下のような「次につながる情報」に着目しています。
レース映像で確認する不利の例
着順を悪化させる「不利」には様々な種類があります。これらを見つけることが、次走で人気が落ちるであろう実力馬を発見する鍵となります。
- スタートでの不利:ゲートの出が悪い「出遅れ」はもちろん、スタート直後に他馬に寄られてしまい、本来取りたかったポジションよりも後ろになってしまう不利。
- 道中での不利:前が壁になってブレーキを踏む「どん詰まり」、直線で全く進路が開かない、あるいは他馬にぶつかるといった物理的な不利。
- 距離的な不利:レースの最初から最後まで、終始コースの外側(3~4頭分外)を回らされ、他馬より明らかに長い距離を走らされている不利。これはタイム差以上にスタミナを消耗します。
レース内容を分析する最大の目的は、その馬の着順が「能力通りだったのか」あるいは「能力以外の要因で決まったのか」を判断し、「次走で狙うべき馬」と「次走で危険な馬」を見極めるためです。
例えば、人気馬が5着に負けたとします。しかしその内容が、ハイペースを先行して粘った結果の5着であったり、直線で深刻な不利(どん詰まり)があった末の5着であったりしたならば、その馬の評価を下げる必要はありません。むしろ、不利な条件で善戦したと評価でき、次走で人気が落ちるようなら絶好の狙い目となります。これが俗にいう「負けて強し」の馬です。
逆に、人気薄の馬が1着になったとします。しかしその内容が、ライバルが不在のスローペースを楽に逃げ切っただけであったり、馬場がその馬だけに極端に味方した結果(例:大雨でパワータイプが勝利)であったりしたならば、その勝利を過大評価してはいけません。次走、メンバーが強化されたり、馬場が回復したりして人気になるようなら、疑ってかかる必要があります。
さらに上級者になると、馬の走り方(走法)と馬場の物理的な相性まで分析します。
データベース内の情報によれば、馬の走法は大きく「ストライド走法」と「ピッチ走法」に分けられることがあります。ストライド走法はフットワークが大きく、地面を滑らせるような走りです。このタイプは、摩擦に弱く、グリップが効くキレイな高速馬場(硬い馬場)に適しています。一方で、ピッチ走法はフットワークが小さく、地面を力強く叩きつけるような走りです。このタイプは、摩擦の強いパワーのいる馬場(時計のかかる馬場、重馬場、ダートなど)でもこなせる傾向があります。この相性を見抜くことで、当日の馬場状態から好走する馬を絞り込むことが可能になります。
「現象」と「本質」を混同しない
そして、当てる人は「レース結果」という現象と、「馬場や展開」という本質を混同しません。
例えば、ある日のレースで差し馬ばかりが上位に来たとします。ここで「今日の馬場は差し馬場だ!」と短絡的に結論づけるのは早計です。まず確認すべきは、「レースのペース」です。もしそのレースが、逃げ馬が競り合って潰れるようなハイペースであれば、前の馬がバテるのは当然であり、結果として差し馬が上位に来ます。これは馬場の性質ではなく、「展開」がもたらした結果です。
逆に、スローペースで前の馬が残った場合も同様です。本当に馬場が前有利なのか、単に展開が楽だっただけなのかを見極める必要があります。
前述の通り、当てる人は、馬場の本質的な性質(摩擦が強いのか、グリップが効くのか)を見極めるためにレースを見ています。競馬新聞の着順という「数字」だけでは絶対に見えない「隠れた能力」や「不利」を発見し、過小評価されている馬(期待値の高い馬)を見つけ出すこと。これが、当てる人の着眼点の核心です。
初心者におすすめの競馬予想方法
- YUKINOSUKE
競馬を始めたばかりの初心者が、いきなり前述したような「馬場読み」や「展開読み」といった複雑な予想に挑戦するのは非常に大変です。これらの要素は経験や多くの情報分析が必要であり、最初から完璧にこなそうとすると競馬の楽しさを見失ってしまうかもしれません。そこで、まずは基本的な情報から予想を組み立て、「当たる喜び」を体験することから始めるのをおすすめします。的中する成功体験こそが、競馬を長く楽しむための最大のモチベーションになります。
そのための第一歩として、「馬券の種類(券種)」を正しく理解することが重要です。競馬には1着を当てる「単勝」、3着以内に入る馬を当てる「複勝」など、JRA(日本中央競馬会)だけでも10種類(WIN5含む)の馬券があります。
いきなり高配当が魅力の「三連単」(1着、2着、3着になる馬を着順通りに当てる)に挑戦したくなるかもしれませんが、これは初心者には推奨できません。なぜなら、18頭立ての場合、その組み合わせは実に4,896通りにもなり、的中させることは極めて困難だからです。「当てる」ことよりも「儲ける」ことを優先しすぎると、的中しない日々が続き、競馬そのものが苦しくなってしまいます。
初心者は「複勝」か「ワイド」から
競馬予想の入門として、まずは的中しやすい以下の2つの券種から始めるのがおすすめです。
- 複勝(ふくしょう)
選んだ馬が3着以内に入れば的中となる馬券です(ただし、出走頭数が7頭以下の場合は2着以内)。的中率が全券種の中で最も高く、「この馬は強いから3着以内には来るだろう」という予想(軸馬選び)の基本的な練習になります。
(注意点)的中しやすい反面、配当(オッズ)は低くなる傾向があります(例:1.1倍~1.5倍など)。大きく儲けるための馬券ではなく、堅実に当てるための馬券です。 - ワイド
選んだ2頭が、ともに3着以内に入れば的中となる馬券です。1着と2着、1着と3着、2着と3着の3通りの的中パターンがあります。「複勝」よりは難易度が上がりますが、それでも他の馬券に比べて当てやすい部類に入ります。「複勝」で軸馬選びに慣れてきたら、次に「軸馬ともう1頭、一緒に3着以内に来そうな馬」を選ぶというステップアップに適しています。人気馬と人気薄の馬の組み合わせで、中配当が狙える魅力もあります。
次に、予想のファクターですが、馬券を選んだら、まずは過去のレース成績(馬柱)を見ることから始めましょう。競馬新聞やアプリに載っている、馬の成績が詰まった表(馬柱)から、以下の点に注目してみてください。
馬柱で注目すべき基本ポイント
- 前走の着順と人気
単純に「前走1着」の馬が強いとは限りません。「8番人気(低評価)だったのに3着(好走)」のように、人気よりも上の着順に来ている馬は、実力をつけてきているか、現在の評価が不当に低い可能性があります。逆に「2番人気(高評価)なのに10着(惨敗)」だった馬は、なぜ負けたのか(距離が合わなかった、馬場が悪かった、不利があった等)を考えるきっかけになります。
- 距離適性
今回走るレースと「同じ距離」での過去の成績は非常に重要です。マイル(1600m)戦ばかりで好成績を収めている馬が、いきなり長距離(2400m)で通用するとは限りません。逆に、前走が長すぎてバテてしまった馬が、今回得意な距離に戻ってきた場合は「巻き返し」が期待できます。
- 騎手
その馬に何度も乗っている騎手(継続騎乗)は、馬の癖を熟知しているという強みがあります。一方で、今回初めて乗る「乗り替わり」でも、成績上位の騎手(リーディングジョッキー)に替わった場合は、陣営(馬主や調教師)の「勝負気配」の表れと見ることもできます。
- 馬場適性
馬柱には、そのレースが「良・稍重・重・不良」のどの馬場状態で行われたかも記載されています。芝のレースであれば芝の成績、ダートのレースであればダートの成績を見るのは基本です。特に「重馬場」や「不良馬場」といった特殊な馬場で好走した経験がある馬は、当日の天候が悪化した場合に狙い目となります。
1番人気を過信しない
初心者が陥りやすいのが、「一番人気だから」という理由だけでその馬を選んでしまうことです。1番人気の馬は、もちろんそのレースで最も強いと支持されている馬ですが、それでも勝率は3割程度と言われています。
JRAのデータ(2023年重賞競走)によると、1番人気馬の勝率は32.2%、3着以内に入る確率(複勝率)も62.0%です。この数字は、「10回に約7回は1着になれず」「10回に約4回は3着以内にも入れない」ことを意味しています。マークが厳しくなったり、馬場が合わなかったり、様々な理由で人気馬は敗れます。絶対的な信頼は置かず、「なぜこの馬が1番人気なのか」を自分の目で馬柱を見て確かめることが大切です。
1番人気については、こちらの記事【競馬の1番人気の複勝で回収率は上がる?データで徹底解説】で詳しく解説しています。
情報源から学ぶ競馬の予想の仕方
競馬予想の基本を学んだら、次は「どこから情報を仕入れるか」が重要になります。現代は本、アプリ、インターネット掲示板など、情報源が溢れています。しかし、これらの情報源にはそれぞれ一長一短があり、その特性を理解して使い分けなければ、かえって予想を混乱させる原因にもなりかねません。
- 本で学ぶ体系的な競馬の予想の仕方
- 知識が深まる競馬勉強アプリの活用術
- Yahoo!知恵袋に見る競馬予想方法
- 2ch(5ch)に見る競馬の予想の仕方
- 自分に合った競馬の予想の仕方を見つける
本で学ぶ体系的な競馬の予想の仕方
- YUKINOSUKE
競馬の予想の仕方を「本(書籍)」で学ぶ最大のメリットは、情報の信頼性が比較的高く、知識を「体系的」に学べる点にあります。
なぜインターネットやSNSが全盛の現代において、あえて本を選ぶのでしょうか。インターネットの情報は、速報性に優れますが、その多くが「断片的な情報」になりがちです。例えば、SNSで「今日の馬場は〇〇産駒が買い!」という情報だけを見ても、「なぜそうなのか」「どんな条件(距離、ペース、枠順)でそうなのか」という最も重要な根拠(ロジック)が欠けていることが少なくありません。
一方で、本(特に専門書)は、「血統」「データ分析」「馬場読み」「調教」など、ある一つのテーマについて、著者が長年培ってきた理論や戦略が一貫した流れで解説されています。多くの場合、編集者や校閲者の目を通っており、情報の信頼性や客観性も担保されやすいという利点があります。
このように、ネットで得た断片的な知識(点)を、本を通じて「なぜそうなるのか」という論理(線や面)として理解し直す作業は、自分なりの予想の「軸」や「思考の枠組み」を構築する上で非常に役立ちます。単なる知識の暗記ではなく、「予想のロジック」そのものを学ぶことができるのです。
本で学ぶ際の注意点(デメリット)
もちろん、本にもデメリットは存在します。最大の注意点は「情報の鮮度」です。特にデータ分析に関する本は、出版から時間が経過すると、近年の馬場の高速化傾向や、新しく登場した種牡馬(父親)のデータに対応できない可能性があります。購入する際は、なるべく出版年月日が新しいものを選ぶか、時代に左右されない普遍的な理論(思考法など)を扱った本を選ぶと良いでしょう。また、購入に費用がかかる点もデメリットと言えます。
競馬本には、主に以下のような分野の専門書があります。自分の興味や、強化したい分野に合わせて選ぶことが上達への近道です。
競馬本の主な分野
- データ・統計分析
「期待値」や「回収率」といった概念を深く学ぶ分野です。どの馬が勝つか(的中率)ではなく、どの馬券が儲かるか(回収率)という視点を提供してくれます。これは競馬を単なるギャンブルから、長期的な収支をプラスにすることを目指す思考へと変えるために不可欠な知識です。
- 血統
「競馬はブラッドスポーツ」と呼ばれる所以を学びます。「ディープインパクト産駒は瞬発力がある」といった大枠だけでなく、新時代の種牡馬(例:キタサンブラック産駒の傾向)や、母の父(ブルードメアサイアー)との組み合わせによる化学反応、馬場適性への影響など、奥深い血のドラマを読み解きます。
- 馬場・コース
「東京の直線は長いから差し有利」といった単純な話ではなく、JRAの馬場造園技術(エアレーション作業など)が近年のレース質(高速化)にどう影響しているか、競馬場ごとの高低差やコーナーの角度がどう有利不利を生むか(例:中山競馬場の急坂)、といった専門的な知見を得られます。
- 思考法・メンタル
競馬は「控除率(主催者の取り分)」があるため、構造的に参加者の多くが負けるゲームです。その中でいかに感情(負けを取り戻したい焦り、人気馬を信じたい願望など)をコントロールし、統計的に優位な馬券だけを冷静に買い続けるか、といった資金管理術(パンクしない方法)を学ぶ分野です。
- 調教・パドック
データとは対照的に、レース直前の馬のコンディション(「仕上がり」や「気配」)を、調教時計やパドック(レース直前に馬が歩く場所)での様子から見抜く技術を解説する本もあります。
このように、多くの本に触れることで、「この考え方は自分に合っているかもしれない」という予想法が見つかるはずです。まずは自分が最も興味を持てる分野(例えば「血統のロマンに惹かれる」「データ分析が好き」など)の本を一冊、じっくり読んでみることをおすすめします。Amazonのレビューを参考にする際は、単なる評価の星の数ではなく、「自分の予想法がどう変わったか」といった具体的な内容が書かれているものを参考にすると良いでしょう。それがあなたの予想の「型」の土台になるはずです。
おすすめの競馬本に関しては、こちらの記事【競馬の本おすすめ13選!初心者から血統派まで目的別に解説】で紹介しています。
知識が深まる競馬勉強アプリの活用術
- YUKINOSUKE
現代の競馬予想において、スマートフォンアプリは欠かせない情報ツールとなっています。競馬新聞やスポーツ紙が長らく情報源の中心でしたが、アプリを活用する最大の利点は、「手軽さ」「速報性」「網羅性」の3点を高いレベルで両立できることにあります。
スマホ一つあれば、通勤中やレース直前のパドック(馬が周回する場所)でも、出走馬情報、リアルタイムのオッズ変動、馬体重の増減、過去のレースデータ、調教タイム、レース映像、専門家によるコラムまで、あらゆる情報にいつでもどこでもアクセスが可能です。特に、新聞ではスペースの都合で掲載しきれない「過去5走より前の全成績」や「詳細な調教時計のラップタイム」、さらには「パトロールビデオ」まで確認できるのは、アプリならではの強みと言えるでしょう。
ただし、競馬アプリと一口に言っても、その目的や機能は様々です。特に定番とされるアプリには、それぞれ明確な特徴があります。
代表的な競馬アプリの例と活用術
- JRA公式アプリ
日本中央競馬会(JRA)が自ら提供しているため、何よりも「情報の正確性」と「信頼性」が抜群です。馬券の購入(即PATやA-PATといったJRAのネット投票サービスとの連携)から、レースのライブ視聴、全レースの結果確認、そして公式のパトロールビデオ閲覧まで、JRAの基本サービスがこのアプリ一つでほぼ完結します。競馬予想の「土台」として、まずインストールしておきたいオールインワンアプリです。(参照:JRA公式スマートフォンアプリ)
- netkeiba
国内最大級の競馬情報ポータルサイトのアプリ版です。最大の特徴は、圧倒的な情報量とコミュニティ機能にあります。JRAだけでなく地方競馬の情報も網羅し、ニュースやコラム、著名な予想家の予想記事が非常に充実しています。初心者向けの競馬用語集や、ユーザー同士が交流できる掲示板機能も活発で、競馬の知識を幅広く深めるのに適しています。無料でも多くの機能が使えますが、有料プランではさらに詳細なデータ分析が可能になります。
- JRA-VAN
JRAの公式データを活用した、より専門的で詳細なデータ分析に強みを持つアプリです。特に、パソコン用の高機能分析ソフト「TARGET(ターゲット)」とデータを連携できるため、長年の競馬ファンやデータ分析を本格的に行いたい「玄人向け」と言えます。調教タイムの詳細な分析や、騎手・種牡馬(父親)・コース条件などを細かく絞り込んだ過去の統計情報を駆使したい場合に強力な武器となります。(※利用には月額料金が必要です)
- オッズパーク/楽天競馬 など
これらは主に「地方競馬」の馬券購入や情報収集に特化したアプリです。JRA(中央競馬)だけでなく、平日も開催されている地方競馬を楽しみたい場合には、別途これらのアプリが必要になることがあります。
これらのアプリを自分の予想スタイルや目的に合わせて使いこなすことで、情報収集の質とスピードは格段に向上します。
アプリ選びの注意点(悪質なアプリの見分け方)
一方で、競馬アプリの数は非常に多いですが、中には利用者の利益を第一に考えていないアプリも存在します。例えば、広告収入を得ることだけが目的で中身が薄いアプリや、「絶対に当たる」といった非現実的な謳い文句で高額な予想情報を販売することが目的のアプリには注意が必要です。
以下のような特徴を持つアプリには、警戒した方が賢明です。
- レビューの評価が不自然に高すぎる(サクラレビューの可能性がある)。
- アプリ起動のたびに、高額な有料プランへの登録を促す広告が何度も表示される。
- 「的中率90%」「回収率500%保証」など、非現実的な的中実績を掲載している。
- 運営会社の情報(所在地や連絡先)が明確に記載されていない。
予想の仕方を学ぶ段階でこうしたアプリに頼ってしまうと、正しい知識が身につかない可能性があります。まずは多くの人が利用しており、運営元が明確なJRA公式やnetkeibaといった信頼性の高い定番アプリから使い始めてみるのが安全です。
Yahoo!知恵袋に見る競馬予想方法
- YUKINOSUKE
競馬の予想方法を学ぶ際、本や専門アプリと並行して、Yahoo!知恵袋のようなQ&Aサイトを参考にする人も少なくありません。その背景には、「専門家には今さら聞きにくい」「同じ目線で悩んでいる人の意見が知りたい」といった心理があります。ここでは、他の競馬ファンが抱いている素朴な疑問や、非常に多様な考え方に触れることができます。
実際に、知恵袋では日々様々なやり取りが行われています。
- 予想方法に関する直接的な質問
「皆さんの競馬予想方法を教えてください」「血統と調教、どちらを重視すべきですか?」 - 具体的な悩み相談
「競馬歴5年でこれまでマイナス100万円です。どうすれば勝てますか?」「スランプから抜け出せません。メンタル管理はどうしていますか?」 - ピンポイントな技術的質問
「パドックでは馬のどこを見ればいいですか?」「『馬場が荒れる』とは具体的にどういう状態ですか?」
このように、専門家には聞きにくいレベルの初歩的な疑問から、多くのファンが共感するであろう切実な悩みまで、幅広く投稿されています。
そして、寄せられる回答(ベストアンサー)も、まさに多種多様です。回答者のスタンスによって、推奨する手法が全く異なります。
知恵袋に見られる多様な回答スタンス
- データ派:「時系列オッズ(売上の推移)の動きに注目しています。特定の時間に不自然な大口投票が入る馬は、何か情報がある可能性があり怪しいです」
- メンタル派:「スランプなら、まず初心に戻って単勝や複勝で勝ち癖をつけましょう。負けが続くと冷静な判断ができなくなります」
- オカルト派(サイン理論):「JRAのカレンダーの色や、その日の世相(大きなイベント)、CMのタレントがサインになっています」
- 騎手派:「馬の能力より騎手の得意・不得意なコースや、馬との相性を重視します」
このように、ロジカルなデータ分析から、ある種のオカルトとも言えるサイン理論まで、世の中には本当に幅広い予想方法が存在することを知ることができます。
知恵袋を活用するメリットは、情報の「正しさ」を求めることではありません。「こんな考え方もあるのか」という視点の「多様さ」を知り、自分の予想方法が偏っていないかを確認するきっかけを得られる点にあると言えるでしょう。
ただし、この「多様さ」は、そのまま「危険性」と表裏一体です。知恵袋の情報を利用する際は、以下の点に最大限の注意を払わなければなりません。
情報の信憑性には最大限の注意を
知恵袋の情報は、あくまで匿名の個人による意見や経験談であり、玉石混交です。回答者が競馬のプロである保証はどこにもなく、科学的根拠のない情報や、単なる思い込みも多く含まれます。「ベストアンサー」に選ばれているからといって、それが「正解」であるとは限りません。
さらに深刻なのは、特定の競馬予想ソフトや高額な情報サイトへ誘導するために、悪質な業者が自作自演で質問や回答を投稿しているケースが紛れ込んでいる可能性も否定できない点です。
例えば、「最近〇〇という予想サイトを使ったら勝てるようになりました」という質問に対し、「私も使っていますが、あのサイトの情報は本物です」といった回答がつくパターンです。これらは、第三者を装って自社サービスを宣伝するステルスマーケティング(ステマ)の典型的な手口です。
回答に記載されている不自然な外部リンクや、具体的な商品名・サイト名を過度に推奨する内容には特に注意し、情報を鵜呑みにせず、あくまで「こんな考え方もあるのか」という参考程度に留めることが賢明です。
2ch(5ch)に見る競馬の予想の仕方
- YUKINOSUKE
2ch(現在は5ch)などの匿名掲示板は、競馬ファンの「忖度のない本音」が集まる場所として、古くから独自の巨大なコミュニティを形成しています。その最大の特徴は、公式メディアや専門誌では決して書かれないような、特定の騎手や厩舎、あるいは競馬予想サイトに対する辛辣な評価が飛び交う点にあります。
メディアが作り出す「建前」や「人気」とは異なる視点、例えば「あの馬は過剰人気すぎる」「この馬は実力の割に人気がなさすぎる」といった、集団心理の「歪み」を指摘する声が見つかることもあります。こうした情報は、世論の逆を突く「逆張り」のヒントになるかもしれません。
また、特に「競馬予想TV!」のような長寿番組や、G1レース当日の実況スレッドは非常に活発です。放送やレースと連動して多くのファンがリアルタイムで意見を交わすため、馬場状態の変化に対する生の声や、レースペースに対する多様な見解など、情報の「鮮度」という点では他の追随を許さない側面も持ち合わせています。
ただし、これらのメリットを享受するには、匿名掲示板が持つ致命的な欠点を理解しておく必要があります。まず、競馬の「予想方法」そのものについて、冷静かつ論理的に深く議論されるスレッドは、意外なほど少ない傾向にあります。なぜなら、匿名掲示板は「予想ロジック」を構築する場ではなく、「結果」に対する批評や感想、あるいはレース前の期待や不安といった「感情」を共有・発散する場としての側面が非常に強いからです。
結果として、話題の中心は「なぜあの馬は負けたのか」という結果論や、特定の馬、騎手、あるいはTwitter(X)で活動する競馬予想家個人に対する批評(時には誹謗中傷に近いもの)になりがちです。
信憑性は担保されない「噂」の集積所
匿名掲示板の情報を利用する上で最も警戒すべきは、その「信憑性の欠如」です。情報の「鮮度」は高いかもしれませんが、情報の「精度」は極めて低い、あるいは皆無に近いと考えるべきです。
Yahoo!知恵袋以上に、投稿者の身元は不明であり、その書き込みが専門的な知見に基づくものか、単なる個人の願望や憶測なのかを区別する手段は一切ありません。すべてが「噂」のレベルであり、感情的な書き込みも多くを占めます。
さらに深刻なのは、意図的な「デマ」や、悪質な競馬予想サイト運営者による「宣伝書き込み」も多く含まれる点です。「このサイトの情報で万馬券が取れた」といった書き込みが、自作自演である可能性は常に考慮しなくてはなりません。
結論として、2ch(5ch)の情報を競馬予想の「根拠」にすることは非常に危険です。馬券の購入は自己責任であり、不確かな情報に振り回された結果、大きな損失を被る可能性もあります。
活用するとしても、「世間は今、この馬をこのように見ているのか」という世論の雰囲気や人気の盲点を把握するための参考資料、あるいは単なる「エンターテイメント」として楽しむ程度に留め、冷静な判断と情報の取捨選択を徹底することが極めて重要になります。
自分に合った競馬の予想の仕方を見つける
- YUKINOSUKE
ここまで様々な競馬の予想の仕方と、情報源について解説してきました。お気づきの通り、競馬予想には「血統」「データ」「馬場」「調教」「騎手」「展開」など、非常に多くのファクター(要因)が存在します。そして、重要なのは、これらの情報を鵜呑みにするのではなく、自分自身で試し、反省し、「自分に合ったスタイル」を確立していくことです。
競馬の予想の仕方に、唯一絶対の「これをやれば必ず勝てる」という正解はありません。なぜなら、人によって競馬に割ける時間、得意な分析手法(数字に強いか、感覚が鋭いか)、そして許容できるリスク(堅実に当てたいか、大穴を狙いたいか)が全く異なるからです。他人の予想方法をそのまま真似しても、これらの前提条件が違えば、うまくいかないことのほうが多いのです。
では、どうすれば自分に合ったスタイルを見つけられるのでしょうか。
「自分だけの軸」を見つける方法
- 自分の「興味」から軸を決める
まずは、自分が最も「面白い」と感じるファクターから入るのが長続きの秘訣です。「血統のロマンに惹かれる」なら血統を、「データ分析が好き」なら過去の統計データを、「馬の様子(パドック)を見るのが楽しい」ならパドック診断を、自分の予想の「軸」に据えてみましょう。 - 自分の「環境」に合わせる
平日は忙しく、レース当日の数時間しか時間を割けない人は、「当日の馬場読み」と「パドック」に特化するスタイルが合うかもしれません。逆に、週中にじっくり時間をかけられる人は、「過去レースのVTR分析」や「調教分析」を中心にしたスタイルが構築できます。 - 自分の「性格」に合わせる
コツコツと的中を重ねたい(的中率重視)なら、前述の通り「複勝」や「ワイド」中心で、堅実な軸馬を見つけるスタイルが向いています。一方、一発の大きなリターン(回収率重視)を夢見るなら、人気薄の馬が好走する可能性(展開利、馬場適性など)を探す穴狙いのスタイルが合っているでしょう。
まずは一つのファクター、例えば「馬場適性だけは誰にも負けないように研究する」「この競馬場のこのコースの血統傾向だけは完璧にする」など、どれか一つを徹底的に研究してみるのが良い方法です。そこで得た確固たる「軸」を基に、他のファクター(騎手や展開など)を肉付けしていくことで、あなただけの予想スタイルが確立されていくはずです。
そして最も重要なのが、「予想したら、必ず結果を検証する」ことです。
「なぜその馬を選んだのか」という根拠を必ず記録しておき、レース後に「なぜ当たったのか」「なぜ外れたのか」を冷静に振り返ります。この「レース回顧」こそが、自分の予想スタイルの精度を上げる唯一の方法です。これを繰り返すことでしか、自分に合ったスタイルは見つかりません。
この記事で解説した要点を参考に、ぜひ自分だけの「予想の型」を見つける旅を始めてみてください。試行錯誤のプロセスこそが、競馬予想の奥深さであり、最大の楽しみでもあります。
最後に、競馬予想の仕方を学ぶ上でのポイントを、この記事の総まとめとして以下に示します。
- 競馬予想の仕方に「絶対の正解」はない
- 最終目標は自分に合った予想スタイルを確立すること
- 予想の第一歩は当日の「馬場読み」から始める
- 馬場の本質(時計・摩擦・グリップ)を分析する
- 馬場適性と馬の能力(6つの要素)のマッチングを重視する
- 騎手の得意戦法と馬の相性も考慮に入れる
- レース展開(ペース)が有利不利を左右する
- VTRで着順に表れない「内容」や「不利」を確認する
- 「負けて強し」の馬を見つけ次走で狙う
- 初心者は的中しやすい「複勝」や「ワイド」から始める
- 1番人気の勝率は3割程度と認識し過信しない
- 本(書籍)は体系的な理論の学習に適している
- 競馬アプリは信頼できる情報源(公式・定番)を選ぶ
- ネット掲示板(知恵袋・5ch)の情報は信憑性を見極め参考程度に
- 悪質な業者や自作自演の書き込みには常に注意する
- 予想と結果を記録し「なぜ当たったか・外れたか」を必ず検証する
- 多様なファクターを組み合わせ総合的に判断する癖をつける










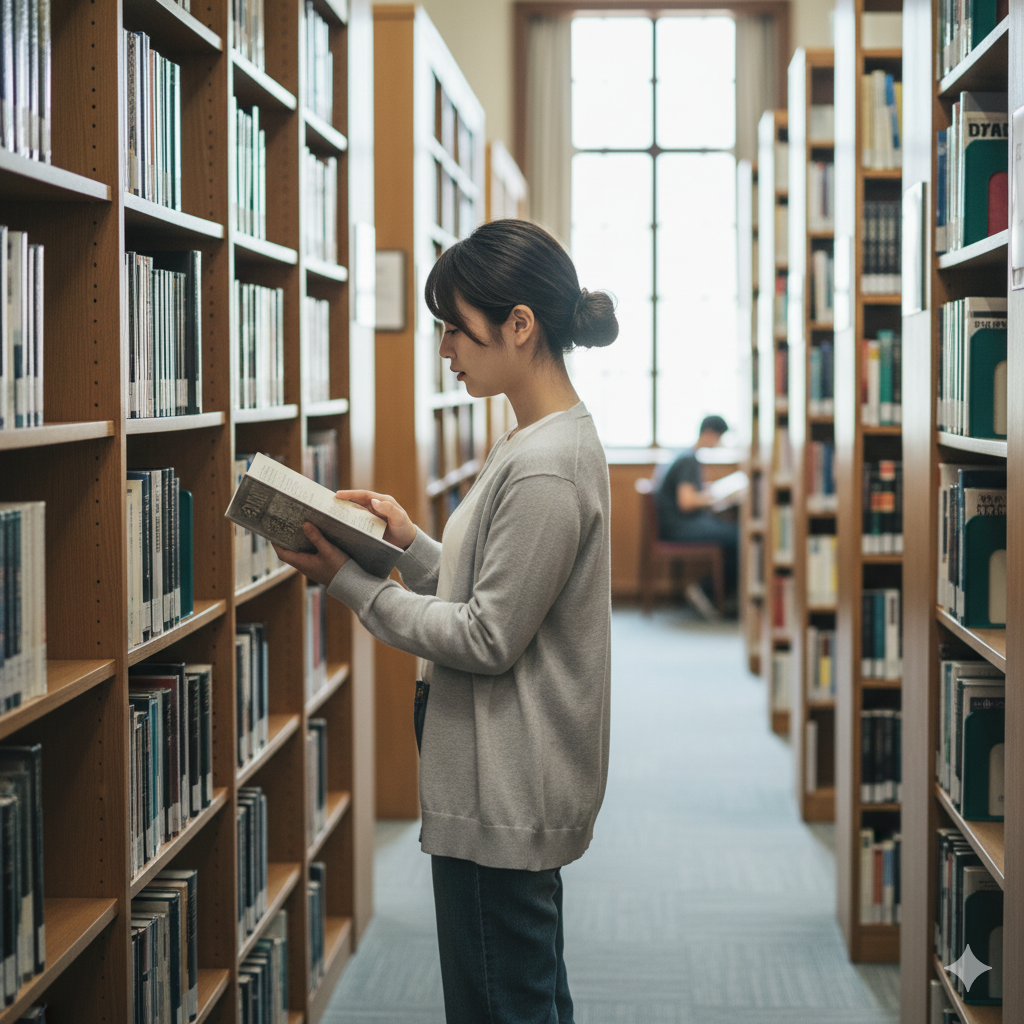
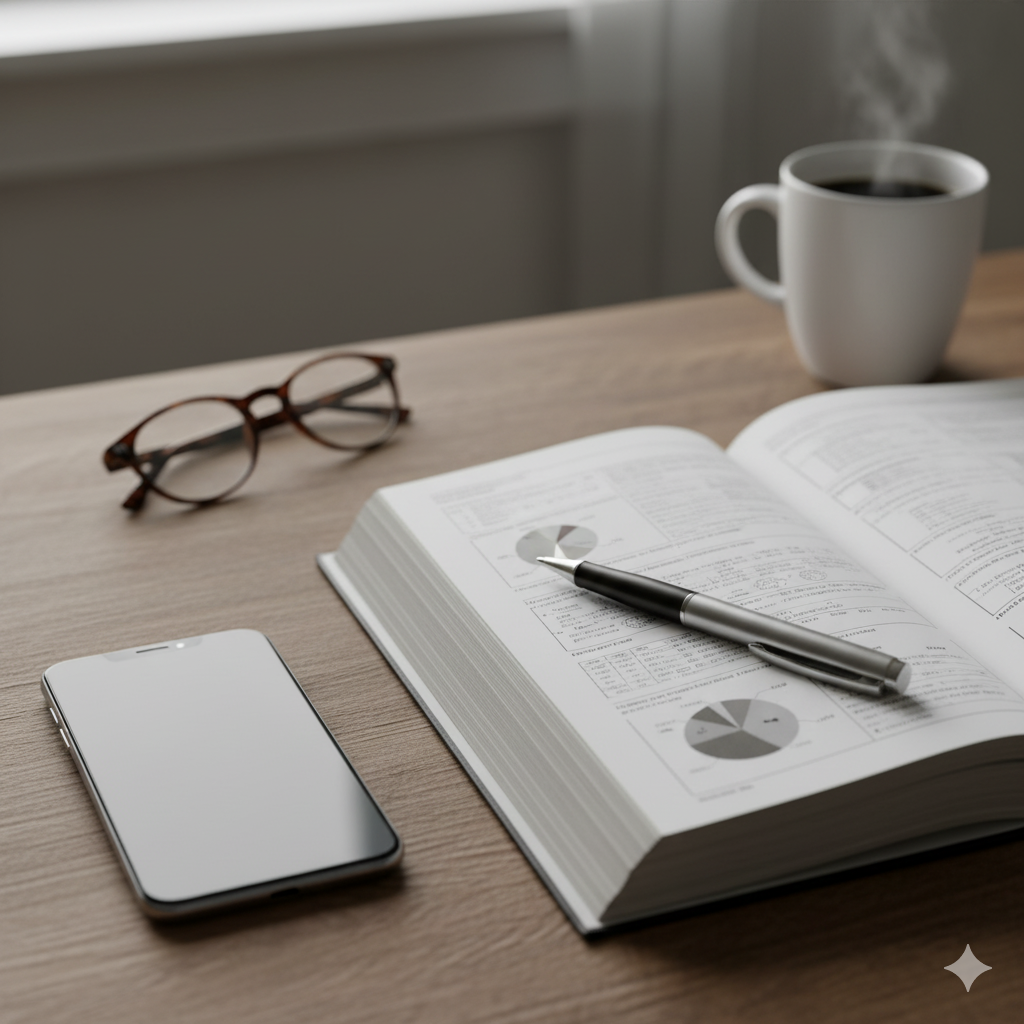





コメント