「京都競馬場 指定席 倍率」と検索されたあなたは、近々開催されるG1レース、特に伝統ある天皇賞春などの特別な日の観戦を計画されているのかもしれません。2023年に待望のグランドオープンを果たした新しい京都競馬場は、以前にも増して魅力的で快適な空間となり、その人気は従来の競馬ファン層を超えて急速に高まっています。このため、注目レース当日の指定席の倍率は、想像以上に高い水準で推移する傾向が顕著です。
実際に、過去の京都競馬場の指定席倍率をデータで見ると、特にグループ席やゴール前の良席は抽選開始後すぐに申し込みが集中します。多くの方が、指定席の抽選で当たらないという厳しい現実に直面していることでしょう。
また、リニューアルによって指定席の種類が非常に多様化しました。例えば、屋外で臨場感を味わえるスマートシートや、天候を問わず快適な屋内のプライベートシートなど、魅力的な選択肢が多数新設されています。しかし、その一方で「結局、指定席でおすすめはどの席なのか?」「それぞれの指定席料金はいくらで、コストパフォーマンスはどうなのか?」といった新たな疑問も生まれているはずです。
さらに、「そもそも指定席が取れなかった場合、当日入場できるのか?」という根本的な疑問や、指定席の当日券の有無、万が一の平日開催の場合の運営方法など、事前に確認しておきたい点は山積みだと推察します。
この記事では、そうした京都競馬場の指定席に関するあらゆる疑問に答えるため、最新の情報を徹底的にまとめました。天皇賞春をはじめとするG1レースの具体的な倍率データから、抽選を突破するための現実的な対策、そして各席種のメリット・デメリットを詳しく比較していきます。あなたの競馬観戦が最高の一日となるよう、必要な情報を網羅的にお届けします。
- G1開催時の指定席の抽選倍率の目安
- 主な指定席の種類とそれぞれの料金
- 抽選に申し込む際の注意点やポイント
- 当日入場やスマートシートに関する情報
京都競馬場 指定席 倍率の基礎知識
- 天皇賞春の指定席の倍率
- 過去の京都競馬場指定席の倍率
- 指定席の抽選が当たらない時の対処法
- 指定席 料金一覧
- 京都競馬場には当日入場できますか?
- 指定席の当日発売とは
天皇賞春の指定席の倍率
- YUKINOSUKE
京都競馬場で開催される数多くのレースの中でも、天皇賞(春)は指定席の倍率が最も高騰するG1レースの一つです。これは単にG1であるというだけでなく、3,200mという芝の長距離で争われる、年に一度の伝統的な競走であり、京都競馬場を象徴する「フラッグシップレース」として特別な位置づけにあるためです。
2023年に完了したグランドリニューアルにより、観戦環境が飛躍的に向上したことも人気に拍車をかけています。この新しく快適なスタンドで、春の古馬最強ステイヤーを決める歴史的なレースを観戦したいと考えるファンが殺到するため、指定席の抽選は極めて厳しくなります。
その実態は、2025年の天皇賞(春)における一般抽選のデータ(締切前日時点)からも明確に読み取れます。
2025年 天皇賞(春) 一般抽選倍率(一部抜粋・締切前日)
- ペアテーブル(2名席):98.1倍
- Lソファ(5名席):91.0倍
- グループテーブル(4名席):59.8倍
- B指定席:10.2倍
- A指定席:9.1倍
- スマートシートA:8.2倍
このように、特にペアテーブルやLソファといったグループ向けの席は、100倍近くと異常なほどの高倍率に達しています。これは、リニューアルで新設されたこれらの席が、単なる観戦席としてだけでなく、「快適な空間で仲間と特別なレジャー体験を共有する場所」としての高い付加価値を持っているためです。加えて、ペアテーブル(28枠)、Lソファ(23枠)など、席数自体が非常に少ないことも、倍率を高騰させる構造的な要因となっています。
また、ゴール前の攻防を間近で見られる伝統的な人気席であるA指定席やB指定席も約10倍と、当選は容易ではありません。さらに注目すべきは、最も席数が多く安価な屋外席であるスマートシートですら、Aエリア(ゴール前)で8倍を超える倍率となっている点です。2024年の天皇賞(春)でもペアテーブルが94.8倍、スマートシートAが9.6倍と高倍率であり、人気は高止まり、むしろ上昇傾向にあることがうかがえます。
JRAカード先行抽選でも高倍率
一般抽選より前に申し込みができる「JRAカード会員先行抽選」は、指定席確保において有利な手段ですが、天皇賞(春)に関しては、その先行抽選ですら非常に高倍率となります。
2025年の先行抽選データ(締切前日)では、ペアテーブルが13.7倍、Lソファが16.4倍でした。この事実は、JRAカード会員であっても当選は狭き門であることを示しています。カード会員の特典は「当選の確約」ではなく、あくまで「抽選のチャンスが一般会員より1回増える」という認識を持つことが重要です。先行抽選でこれだけの倍率になるということは、それだけ多くの会員が落選し、続く一般抽選に回ってくる席数がさらに少なくなることを意味しており、一般抽選の厳しさを一層際立たせています。
過去の京都競馬場指定席の倍率
- YUKINOSUKE
前述の通り、天皇賞(春)は京都競馬場で開催されるレースの中で最も倍率が高騰しますが、だからといって他のG1レースの指定席が簡単に取れるわけではありません。特に、春の天皇賞と並んで京都競馬場を代表するクラシックレースである「菊花賞(G1)」や「秋華賞(G1)」も、指定席の倍率は非常に高くなります。
まず、牡馬クラシック三冠の最終戦として知られる菊花賞のデータを見てみましょう。これもまた、3,000mの長距離で争われる歴史ある伝統の一戦です。2025年の一般抽選(締切前日時点)の倍率は以下の通りです。
2025年 菊花賞 一般抽選倍率(一部抜粋)
- Lソファ:59.3倍
- ペアテーブル:49.0倍
- B指定席:7.1倍
- A指定席:6.9倍
- スマートシートA:6.1倍
ご覧のように、Lソファやペアテーブルといったグループ席は50倍から60倍近い水準です。天皇賞(春)の100倍近い数値と比較すれば低く見えるかもしれませんが、これでも当選するのは極めて困難な数字であることに変わりありません。
また、ゴール前のA指定席やB指定席も約7倍、屋外のスマートシートAですら約6倍となっています。G1開催日においては、どの席種であっても「簡単に取れる席」は存在しないことがよくわかります。
次に、牝馬三冠の最終戦である秋華賞も同様に高い人気を誇ります。2025年の一般抽選(締切前日時点)では、Lソファが46.4倍、ペアテーブルが34.5倍と、やはりグループ席の確保は至難の業です。
レースの「物語性」が倍率を左右する
ここで注意したいのは、これらの倍率はあくまで「例年のG1」としての数値である点です。競馬のG1レースは、その年ごとの「物語性」によって注目度が大きく変動します。例えば、2023年の秋華賞のように、無敗の三冠牝馬誕生がかかった歴史的なレースとなった場合、メディアの注目度やファンの熱気は通常年を遥かに凌ぎます。そのような年は、秋華賞の倍率が菊花賞や天皇賞(春)に匹敵する水準まで跳ね上がる可能性も十分に考えられます。倍率は固定ではなく、その年の出走馬や状況によって大きく変動するものと理解しておきましょう。
G1以外の通常開催日(平場開催)
では、G1が開催されない通常の土日開催日はどうでしょうか。この場合、状況は一変します。競馬ファンの間では「平場(ひらば)開催」と呼ばれるこれらの日は、指定席の倍率はG1開催日とは比較にならないほど低くなります。
多くの場合、事前の抽選自体が行われず、開催週の木曜日や金曜日から「残席販売」として先着順で販売されます。席の細かな位置に強いこだわりがなければ、開催日直前でも指定席を確保できるケースがほとんどです。初めて京都競馬場の指定席を試してみたいという方は、まずこの通常開催日で体験してみることをお勧めします。
通常開催日でも注意すべき点
ただし、通常開催日であっても注意点が二つあります。一つ目は、気候の良い春(4月~5月)や秋(10月~11月)の開催日です。これらの時期は、屋外のスマートシートが非常に人気を集め、抽選にはならなくとも先着販売で早めに売り切れてしまうことがあります。
二つ目は、G1レースの前哨戦(ぜんしょうせん)となるG2レースが開催される日です。例えば、菊花賞トライアルの「神戸新聞杯」や、日本ダービートライアルの「京都新聞杯」などが開催される日は、G1ほどではなくとも通常の平場開催よりは格段にファンの関心が高まります。これらの日も、早めに席の状況を確認するのが賢明でしょう。
指定席の抽選が当たらない時の対処法
- YUKINOSUKE
前述のセクションで見た通り、天皇賞(春)のような人気G1では、倍率が100倍近くに達することもあります。これほどの高倍率になると、「G1の指定席抽選が当たらない」と悩むのは当然で、むしろ落選が当たり前の世界です。
しかし、単に運を天に任せて申し込みを繰り返すだけでは、当選の確率は上がりません。少しでもその確率を引き上げるために、現実的に取り得る3つの対処法を、優先順位の高い順に詳しく解説します。
1. JRAカード会員になり、抽選機会を増やす
G1指定席を本気で確保したいと考えるなら、最も基本的かつ効果的な方法が「JRAカード会員」になることです。これには年会費(初年度無料、次年度以降1,375円(税込))が発生しますが、それ以上に大きなメリットがあります。(出典:JRAカード公式サイト)
最大のメリットは、一般のネット会員では申し込めない「JRAカード会員先行抽選」に参加できる点です。これにより、抽選のチャンスが以下の2回に増えます。
- 1回目:JRAカード会員先行抽選(一般会員より申込者が少ない枠で勝負できる)
- 2回目:一般抽選
仮に先行抽選で落選した場合でも、その後に実施される一般抽選に再度申し込むことが可能です(※システム上、先行抽選の申し込み内容を引き継いで一般抽選に自動で申し込まれることが多いですが、都度確認が必要です)。
ただし、前述の天皇賞(春)のデータで見た通り、G1開催日では先行抽選ですら10倍を超える高倍率になることも珍しくありません。JRAカードは「当選を確約する魔法のカード」ではなく、「当選の確率を少しでも上げるための最も正攻法な手段」と理解しておくことが重要です。年に何度も競馬場に行く方や、G1観戦のチャンスを最大化したい方にとっては必須の対策と言えるでしょう。
2. 同行者と協力し、申し込み口数を増やす
当選確率を物理的に高める、最も強力な方法が「同行者と協力する」ことです。JRAの指定席ネット予約システムでは、G1開催日でも1人につき2席まで(席種によっては1卓や1部屋単位)申し込むことができます。
この時、申込者は「同行者」の情報を登録する必要があります。もし、一緒に行く予定のBさんもJRAのネット予約会員である場合、以下の2パターンの申し込みが可能です。
- パターン1:Aさん(申込者) + Bさん(同行者) で申し込む
- パターン2:Bさん(申込者) + Aさん(同行者) で申し込む
この2パターンでそれぞれ申し込むことで、単純計算で抽選機会が2倍になります。もし、Aさん・Bさん両方がJRAカード会員であれば、この2パターンを「先行抽選」と「一般抽選」の両方で行使できるため、最大で4回の抽選機会を得られる計算になります。
なお、同行者の登録には氏名、生年月日、電話番号などの個人情報が必要となるため、あらかじめお互いに情報を共有しておく必要があります。
この方法で両方のパターンが当選した場合でも、不正扱いにはなりません。JRAのシステム上、重複当選は起こり得るものとされています。その際は、どちらか一方の申し込みを「購入履歴」または「抽選履歴」からキャンセルすれば問題ありません(通常、支払い期限までがキャンセル期限となります)。
3. 残席販売(キャンセル待ち)に賭ける
これは、すべての抽選に落ちた場合の「最終手段」です。一般抽選の結果発表後、当選者には支払い期限が設けられています。この期限までに支払われなかった席(いわゆる「うっかり入金忘れ」)や、前述の協力申し込みで重複当選した人が手放した席は、「残席販売」として先着順で再販売されます。
この残席販売は、G1開催日の場合、一般抽選の申し込み締切の翌週月曜日18時頃(例:天皇賞春の場合は4月28日(月)18:00~)から開始されることが多いです。
ただし、G1開催日において、この方法で席を確保できる可能性は極めて低いと考えるべきです。理由は2つあります。
- そもそもG1開催日の人気席種でキャンセルが出ること自体が稀であること。
- 販売開始と同時に、抽選に外れた全ての人が一斉にアクセスするため、サイトが非常に重くなり、接続できた瞬間にすべて売り切れている「瞬殺」状態になることが常であること。
これは熾烈な「早押し合戦」であり、戦略というよりは奇跡に近いものです。過度な期待はせず、「もし運良くサイトに繋がったらラッキー」程度に考えておくのが賢明です。
指定席の料金一覧
- YUKINOSUKE
京都競馬場の指定席料金を調べる際、まず理解しておくべき最も重要なポイントは、料金が「開催日によって大きく変動する」という事実です。これは、G1レースのような注目度の高い日と、通常の開催日(競馬ファン用語で「平場開催」とも呼ばれます)とでは、座席に対する需要がまったく異なるためです。
この需要の差に基づき、京都競馬場の指定席料金は、主に以下の3段階の価格体系で設定されています。
京都競馬場の3段階料金システム
- 通常開催日 最も基本となる安価な料金設定です。G1やG2といった重賞レースが開催されない、いわゆる平場開催の土日を指します。
- G1開催日 「秋華賞」や「マイルチャンピオンシップ」、「エリザベス女王杯」など、G1レースが開催される日の料金です。需要が一気に高まるため、通常開催日よりも価格が引き上げられます。
- 特定G1開催日(天皇賞・春、菊花賞) 前述の通り、G1の中でも「天皇賞(春)」と「菊花賞」は、京都競馬場の長い歴史を象徴する特別なレースです。これらは他のG1を凌ぐ最高レベルの注目度と人気を誇るため、最も高い料金(特定G1料金)が設定されています。
ここでは、代表的な席種について、これら3パターンの料金目安を一覧表で紹介します。
主な指定席の料金目安一覧
| 席種 | エリア | 通常料金 | G1開催料金(例:秋華賞) | 特定G1料金(例:天皇賞春) |
|---|---|---|---|---|
| A指定席 | ゴールサイド4階(屋内) | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
| B指定席 | ゴールサイド4階(屋内) | 3,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| スマートシートA | ゴールサイド(屋外) | 600円 | 900円 | 1,200円 |
| スマートシートB | ゴールサイド(屋外) | 400円 | 600円 | 800円 |
| スマートシートC | ゴールサイド(屋外) | 400円 | 600円 | 800円 |
| プライベートシート | ステーションサイド5・6階(屋内) | 1,500円 | 2,500円 | 3,000円 |
| ペアテーブル(2名) | ステーションサイド6階(屋内) | 3,000円(2席) | 5,000円(2席) | 6,000円(2席) |
| Lソファ(最大5名) | ステーションサイド6階(屋内) | 7,500円(1卓) | 12,500円(1卓) | 15,000円(1卓) |
| 駒見小路(最大4名) | ステーションサイド7階(屋内) | 12,000円(1部屋) | 20,000円(1部屋) | 24,000円(1部屋) |
料金に関するご注意
上記の表はあくまで一例であり、料金体系はJRAの判断によって変更される可能性があります。(※表内のG1料金はデータベースの情報に基づき作成した参考例です)
また、グループ席(ペアテーブル、Lソファ、駒見小路など)は1人単位ではなく、「1卓」「1部屋」単位での発売となる点にご注意ください。例えば、Lソファ(最大5名)を3人で利用する場合でも、1卓分の料金(通常7,500円)が必要となります。
最新の正確な料金については、必ずJRA公式サイトの指定席情報ページをご確認ください。
指定席料金には「入場料」がすべて含まれます
見落としがちな点ですが、JRAの指定席料金には、当日の入場料がすべて含まれています。
例えば、通常開催日の入場料は200円ですが、G1開催日には500円、あるいはそれ以上に設定されることもあります。指定席券を持っていれば、これらの入場料を別途支払う必要は一切ありません。
特にスマートシートA(通常600円)のような安価な席は、実質的な席代が400円(600円 – 入場料200円)と、非常にコストパフォーマンスが高いことがわかります。G1開催日(スマートシートAが1,200円、入場料500円の場合)でも、実質的な席代は700円となり、お得感があると言えるでしょう。
京都競馬場には当日入場できますか?
- YUKINOSUKE
指定席の抽選にすべて落選してしまった時、多くの方が「もう当日は競馬場に入ることすらできないのだろうか?」という不安に駆られるかもしれません。しかし、結論から申し上げますと、指定席券がなくても京都競馬場に当日入場することは可能です。
ただし、その入場方法と、G1開催日における重大な注意点を理解しておく必要があります。
JRAの公式案内によれば、京都競馬場への入場方法は、大きく分けて以下の3パターンが存在します。
京都競馬場への3つの入場方法
- 「指定席ネット予約」を利用する 本記事で解説している通り、事前に指定席券を購入して入場する方法です。この場合、指定席料金に当日の入場料も含まれています。
- 「入場券ネット予約」を利用する 指定席は確保せず、「入場する権利」だけを事前にネット予約(購入)する方法です。
- 「入場券の当日現金発売」を利用する 競馬場の入場門に設置されている窓口で、当日の入場券を現金で購入する方法です。
つまり、指定席の抽選に外れた場合でも、上記の2または3の方法で「入場券」さえ手に入れれば、競馬場内に入り、レースを観戦すること自体はできます。
入場券のみで入場した場合、観戦場所はゴール前の立ち見エリア、パドック周辺、またはリニューアル後も一部残されているステーションサイド(旧ビッグスワン)の屋外自由席(ベンチ)などになります。ただし、G1当日のこれらのエリアは、朝の開門と同時に場所取り合戦が始まるほどの激しい混雑が予想されることは覚悟しておく必要があります。
最重要:G1開催日の入場券に関する重大な注意点
ここで最も注意しなければならないのが、天皇賞(春)や菊花賞といった特定のG1開催日、あるいは2023年のグランドオープン期間中のような、特に多くの来場者が見込まれる日の運用です。
これらの特定日においては、場内の著しい混雑による事故を防ぐ「安全対策」のため、3の「入場券の当日現金発売」が中止されるケースが常態化しています。リニューアルによって施設は快適になりましたが、安全に収容できる人数には限りがあるため、入場者数そのものを厳しくコントロールする必要があるためです。
G1当日に起こり得る「最悪のシナリオ」
もし、「入場券の当日現金発売」が中止された日に、2の「入場券ネット予約」分も事前にすべて完売してしまった場合、どうなるでしょうか。
その答えは、「当日、競馬場に足を運んでも、入場券を持っていない人は一切入場できない」という事態が発生します。遠方からわざわざ京都まで来たのに、競馬場の門の前で入場を断られるという、最も避けたい状況です。実際に、2023年のリニューアルオープン直後のG1開催日などでは、この措置が取られました。
したがって、G1開催日に指定席が取れなかった場合の次善の策は、ただ一つです。 それは、「指定席の抽選に落選したことが判明したら、即座に『入場券ネット予約』の発売スケジュールを確認し、必ず事前に入場券を確保しておく」ことです。
G1開催日の入場券ネット予約は、指定席の抽選結果発表後、または開催週の初め頃から開始されることが多いです。この貴重な「入場する権利」を逃さないよう、JRA公式サイトの入場・発売情報を常に確認する習慣をつけておくことを強く推奨します。
指定席の当日発売とは
- YUKINOSUKE
「指定席の当日発売」という言葉については、現在、非常に注意が必要です。なぜなら、かつての競馬場のイメージとは運用実態が大きく異なっているためです。
以前は、開催日当日の早朝から競馬場の専用窓口に並び、先着順で当日分の指定席を購入するという方法が存在しました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を契機とした運営の見直しや、JRA全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進により、この「窓口での当日発売」は原則として廃止されました。
現在のJRAの指定席は、すべて「指定席ネット予約」サイトを通じた事前販売が基本となっています。したがって、G1開催日に限らず、通常開催日であっても、競馬場の窓口で直接「今日の指定席をください」と申し出ることは原則できません。
では、「当日発売」は完全に存在しないのかというと、言葉の意味を少し変えた「当日まで購入が可能な席」は存在します。それが、前述のセクションでも触れた「残席販売」です。
これは、抽選販売で申し込みがなかった席(売れ残り)や、当選したにもかかわらず期限までに入金されなかった「キャンセル席」を、開催日当日までJRAのネット予約サイト上で先着順で販売する仕組みです。スマートフォンさえあれば、JRAの会員登録とクレジットカード決済で、競馬場に向かう途中や、すでに入場券で入場した後でも、空きさえあれば購入が可能です。
G1開催日の残席販売(当日発売)の現実
しかし、本記事で繰り返し解説している通り、天皇賞(春)や菊花賞といったG1開催日に関しては、状況がまったく異なります。
これらの日は、抽選の段階で倍率が数十倍から100倍近くに達するため、そもそも売れ残る席が存在しません。また、当選したファンが入金忘れをするというキャンセルも極めて稀です。万が一、ごくわずかなキャンセル席が残席販売に出たとしても、抽選に外れた膨大な数の人々が販売開始と同時にアクセスするため、サイトに繋がった瞬間にすべて売り切れている「瞬殺」状態となります。
したがって、G1開催日において、「当日の残席販売で指定席を買う」という選択肢は、現実的な計画として成立しません。「G1の指定席は、事前の抽選で決まる」というのが、現在の厳然たる事実です。
唯一の例外:「パークウインズ」開催日
「当日発売」が現実的な選択肢となる唯一の例外が、「パークウインズ」として営業する日です。
パークウインズとは、京都競馬場自体ではレースが開催されず、他の競馬場(例えば、中山競馬場の「有馬記念」や東京競馬場の「日本ダービー」など)で行われるレースの馬券発売と中継のみを行う日のことを指します。
これらの日は、京都でのG1開催日ほどの混雑にはなりませんが、世紀の一戦を良い環境で見たいという指定席の需要は確実に存在します。そのため、ステーションサイド6階など一部の指定席が、抽選を経ずに「当日ネット販売(先着順)」されるケースが多いです。この場合も、窓口ではなく「ネット予約サイト」で購入する点は同じですが、G1開催日とは異なり、比較的容易に席を確保できる可能性があります。
パークウインズに関しては、こちらの記事京都競馬場パークウインズ徹底ガイド!無料で楽しむコツで詳しく解説しています。
京都競馬場の指定席の倍率と座席選び
- おすすめの指定席の席種
- スマートシートの概要
- プライベートシートとは
- 平日開催の指定席
- 京都競馬場指定席の倍率を総括
おすすめの指定席の席種
- YUKINOSUKE
2023年のリニューアルオープンに伴い、京都競馬場には多種多様な指定席が新設されました。これにより、観戦者のニーズに合わせて非常に細かく席を選べるようになったのが大きな特徴です。しかし、選択肢が増えたからこそ「どの席が自分に合っているのかわからない」という方も多いでしょう。
ここでは、代表的な観戦スタイルを4つの目的に分類し、それぞれに最適な「おすすめ」の席種を、メリットとデメリット(注意点)を交えながら詳しく解説していきます。ご自身の観戦スタイルや予算、同行者に合わせて最適な席を見つけてみてください。
1.【目的別】ゴールの瞬間を間近で見たい(屋内・快適性重視)
該当席種:A指定席・B指定席(ゴールサイド4階)
競馬の醍醐味であるゴール前の激しい攻防を、最高の環境で観戦したい方向けの席です。ゴールサイドスタンドの4階、ガラス張りの屋内席で、まさに特等席と言えます。
- メリット: 最大の利点は、天候に一切左右されない快適性です。真夏の猛暑日でも真冬の寒波の日でも、空調の効いた室内で優雅にレースを楽しめます。全席にコンセントが完備されているため、一日中スマートフォンで情報収集やネット投票を行っても充電の心配がありません。A指定席はゴール板のほぼ正面、B指定席はA指定席より少し4コーナー寄り(ゴール手前)に位置し、どちらも素晴らしい眺望を誇ります。
- デメリット・注意点: まず、料金が最も高く設定されています(通常4,000円/3,000円、天皇賞春8,000円/6,000円)。当然、G1開催日の抽選倍率も高くなります。また、ガラス張りで密閉された空間のため、屋外スタンドで響き渡るような大歓声や馬の蹄音(ていおん)は直接聞こえません。静かに観戦できる反面、臨場感や一体感を最優先する方には物足りなく感じる可能性があります。
2.【目的別】低価格で臨場感を味わいたい(屋外・コスパ重視)
該当席種:スマートシート A・B・C(ゴールサイド1階~3階)
「指定席は欲しいけれど、価格は抑えたい」「競馬場の一体感や歓声を肌で感じたい」という方に最適な、最もスタンダードな屋外席です。
3.【目的別】グループでワイワイ楽しみたい(レジャー・体験重視)
該当席種:Lソファ(ステーションサイド6階)、駒見小路(ステーションサイド7階)など
レース観戦だけでなく、友人や家族と一日中楽しく過ごす「レジャー」としての側面を重視する方向けの席です。
- Lソファ: 最大5名まで利用可能なグループ用ソファ席です。席からレースを観戦でき、テーブルにはモニターも設置されています。自宅のリビングでくつろぐように、仲間と会話を楽しみながら競馬観戦ができる「体験価値」が魅力です。G1開催日は抽選倍率が最高レベルに達しますが、それはこの席の快適さと、23枠という席数の少なさに起因します。
- 駒見小路: ステーションサイド最上階(7階)にある、最大4名の半個室型の特別な空間です。「おしゃれな旅館のよう」とも評される高級感とプライベート感が特徴で、専用モニターやソファも完備されています。テラスからはコース全体(向こう正面まで)を見渡せますが、7階という高さと位置からゴール前の攻防は直接見えません。レースの決着は室内のモニターで確認します。価格は高額ですが、4人で利用すればA指定席と変わらないコスト感になることもあり、特別な日の利用に最適です。
4.【目的別】快適な室内で馬券に集中したい(馬券派・快適性重視)
該当席種:プライベートシート(ステーションサイド5・6階)
「ゴールの瞬間を見ることよりも、快適な環境でじっくりと予想や馬券検討をしたい」という、いわゆる「馬券派」の方に最適な屋内席です。
どの席を選ぶかは、あなたが競馬観戦に何を一番求めるかによって決まります。「ゴールの興奮」ならA/B指定席かスマートシートA、「価格と臨場感のバランス」ならスマートシート、「仲間との時間」ならLソファ、そして「馬券への集中」ならプライベートシートが、あなたの最適解になるかもしれません。ご自身のスタイルに合った席を選んで、新しい京都競馬場での一日を楽しんでください。
スマートシートの概要
- YUKINOSUKE
スマートシートは、2023年にリニューアルされた京都競馬場において、最も席数が多く、スタンダードな指定席として位置づけられています。旧スタンドの一般観覧席の多くが、この背もたれ付きの屋外席に置き換わりました。ゴールサイドの1階から3階という、レースを間近に感じられるエリアに設置されており、競馬場の熱気や臨場感をダイレクトに味わえるのが最大の特徴です。
屋内指定席のような快適設備はありませんが、その分、料金が安価に設定されています。ここでは、スマートシートのメリットと、利用する上で必ず知っておくべき注意点を詳しく解説します。
メリット
- 圧倒的なコストパフォーマンス スマートシート最大の魅力は、その価格設定にあります。通常開催日であれば、ゴール前のAエリアでも600円、B・Cエリアなら400円(いずれも入場料込)で利用できます。前述の通り、指定席料金には入場料(通常200円)が含まれているため、実質的な席代は200円から400円程度となり、非常に高いコストパフォーマンスを誇ります。G1開催日でも1,000円前後に設定されており、手軽に自分だけの席を確保できる点は大きな利点です。
- 屋外ならではの臨場感 屋外に設置されているため、競馬の醍醐味である「音」と「空気感」を全身で感じられます。馬群が目の前を通過する際の地鳴りのような蹄音(ていおん)、騎手たちの声、そしてメインレースで響き渡る大歓声との一体感は、ガラス張りの屋内席では決して味わうことのできない体験です。
- 選べる3つの観戦エリア スマートシートは、位置によってA・B・Cの3つのエリアに区分されています。Aエリアはゴール板の正面で、白熱のゴール前攻防を見たい方に最適です。Bエリアは大型ターフビジョンの正面に位置し、レース全体の展開をビジョンで追いながら、目の前も馬が通過するという実用的な観戦が可能です。Cエリアはゴール板を過ぎた位置になりますが、レース後の競走馬が引き揚げてくる場所や、ウィナーズサークル(表彰式を行う場所)に近いという利点があります。
デメリット・注意点
- 天候の影響を直接受ける これは屋外席の宿命であり、最大のデメリットです。雨の日は当然濡れますし、夏の開催日(特に7月~9月)は西日がターフビジョンに反射したり、日差しを遮るものがないため猛烈な暑さに見舞われます。逆に冬の開催日(1月~2月)は、スタンドのコンクリートからの底冷えと風で、防寒対策が必須となります。
- 雨天時の対策と「安全席」 雨を避けたい場合、1階や2階の前方列(「あ列」など)は屋根がほとんど機能しないため、雨具が必須です。データベースの情報によれば、比較的濡れにくいのは、スタンドの屋根が深くまでかかっている3階席、その中でも「さ列」よりも後方の席とされています。ただし、これは小雨程度までの話であり、台風や強風を伴う荒天の場合は、後方席であっても雨が吹き込む可能性は十分にあります。
- 座席の設備 椅子は背もたれ付きですが、材質は硬めのプラスチック製です。長時間快適に座り続けるためのクッション性はありません。特に気温が低い日は座面が非常に冷たくなるため、携帯用の座布団やブランケットを持参することを強く推奨します。なお、各席の横にはドリンクホルダー兼用の小さなサイドテーブルが設置されており、これは非常に便利です。
- 馬券購入の動線 リニューアル後の京都競馬場は、JRAが推進するキャッシュレス投票「UMACA」の利用が前提となっているフロア設計が見られます。特に2階のフロアは、UMACA専用の発券機のみが設置されているエリアが多くなっています。このため、昔ながらの現金(紙馬券)で購入したい方は、1階または3階の現金発券機まで移動する必要があり、レース締切間際は混雑で焦る原因にもなります。現金派の方は、あらかじめ1階か3階のスマートシートを選ぶか、この機会にUMACAに登録するのが賢明です。
おすすめのエリア考察(データベース情報より)
データベースの情報によると、スマートシートの中でも特に利便性と快適性(雨対策)のバランスが良い「狙い目のエリア」があるとされています。それは、スマートシートA(ゴール前エリア)の3階席、その中でも後方にあたる「せ列」から「に列」の、柱番号11番から12番付近(座席番号では90番台)です。
この場所が推奨される理由は、以下の点が挙げられます。
- 前述の通り、3階の後方であるため、スタンドの深い屋根によって雨の影響を受けにくいこと。
- 3階という高さが、レース全体を見渡しやすく、同時にゴール板と大型ターフビジョンの両方を視界に入れやすいこと。
- 階段やエスカレーターからのアクセスが良く、さらに3階にある現金発券機や、無料の給茶コーナーにも近いこと。
パドックへの移動距離も考慮すると、3階は各施設へのアクセス動線が非常に優れており、G1以外の開催日であれば、最もバランスの取れたフロアと言えるかもしれません。屋外観戦の感動を何倍にも高めるためには、双眼鏡で競馬が変わる!おすすめの倍率と選び方を徹底解説の記事も参考にして下さい。「せっかく競馬場に来たのに、ゴール前が豆粒にしか見えない…」といった消化不良を最高の臨場感に変えてくれるアイテムになるはずです。
プライベートシートとは
- YUKINOSUKE
プライベートシートは、ステーションサイド(旧ビッグスワン側)の5階および6階に設置されている、全席屋内の指定席です。2023年のリニューアルに際して新設された席種で、その高い快適性と集中できる環境から、競馬にじっくりと向き合いたいファンを中心に非常に高い人気を集めています。
この席の最大の特徴は、「ゴール前の眺望」をあえて切り捨て、代わりに「個人の快適な執務空間(ワークスペース)」を提供することに特化している点です。ここでは、プライベートシートが持つ独自のメリットと、利用する上で必ず理解しておくべき注意点(割り切りが必要な点)を詳しく解説します。
プライベートシートのメリット
- プライベート性の高い半個室空間 座席は一人ひとりパーティション(間仕切り)で区切られた半個室型(ブース型)になっています。これにより、隣の席を気にすることなく、競馬新聞やノートパソコンを広げて予想に没頭することができます。競馬場特有の喧騒から切り離され、静かに集中できる環境は、他の席種にはない大きな利点と言えます。
- 充実した設備と快適な椅子 A指定席やB指定席と同等と見られる、クッション性の高い快適な椅子が採用されています。各ブースにはコンセントが完備されており、スマートフォンの充電はもちろん、PCを一日中利用することも可能です。足元には荷物用フックも備わっています。
- 卓越したコストパフォーマンス 前述の通り、ゴール前のA指定席(通常4,000円)やB指定席(通常3,000円)と比較して、プライベートシートは通常1,500円(G1開催時でも3,000円程度)と、安価な料金設定です。快適な椅子と電源付きの個人ブースをこの価格で終日利用できるのは、非常に高いコストパフォーマンスと言えます。
- 天候に一切左右されない快適性 全席が完全屋内にあるため、真夏の猛暑日や、雨、雪、強風といった悪天候の日でも、空調の効いた快適な環境で一日を過ごせます。これは、屋外のスマートシートと比較した際の明確な優位点です。
- グループ利用への柔軟な対応 5階の一部ブロック(A~Dブロック)では、隣り合う席の間の仕切りがスライド式になっています。友人同士で2席を予約した場合、この仕切りを開けることで会話をしながら楽しむことも可能です。さらに、これとは別に「プライベートシート4名グループ」や「6名グループ」といった専用の発売枠もあり、通路を挟んで隣り合った席をまとめて確保することもできます。
デメリットと利用上の注意点
- 【最重要】席からコースが一切見えない この席を選ぶ上で、最も重要で、唯一とも言える割り切りが必要です。それは、自分のブース(座席)からはコースが一切見えないということです。ブースは馬場とは反対側を向いているか、フロアの内側に配置されています。レース観戦は、席の近くに多数設置されているモニターで行うのが基本となります。
- 生のレース観戦は「共有テラス」から もし生のレースを直接見たい場合は、席を立ち、フロアに設けられた屋外の「共有テラス」へ移動する必要があります。当然、自分のブースで予想しながら、同時に生のレースを見ることはできません。
- 共有テラスは「4コーナー寄り」 この共有テラスは、ステーションサイド(4コーナー寄り)に位置しています。そのため、ゴール前の攻防や、ゴール板(決勝線)を直接見ることはできません。レースの決着は、テラスに設置されたビジョンか、室内のモニターですぐに確認することになります。
- テラスならではの眺望 一方で、このテラスからは、ゴール前とは異なる魅力的な眺望が楽しめます。全馬が一斉になだれ込んでくる4コーナーから直線入り口の迫力ある攻防や、ダート1800mのスタート地点が目の前にあるため、スタート前の輪乗りやゲートインの緊張感を間近で感じることができます。
- UMACA(キャッシュレス投票)推奨の環境 フロア内の現金券売機は、5階に1箇所のみなど、設置数が非常に限られています。レース直前は大変混雑するため、馬券の購入はJRAのキャッシュレス投票システム「UMACA」の利用を強くお勧めします。
結論として、プライベートシートは「ゴール前の興奮をライブで見たい」という方には明確にお勧めできません。この席は、むしろ「快適な自分だけの基地(ベースキャンプ)」です。
ゴール前の眺望よりも、天候に左右されない快適な環境で、電源と机を使ってじっくりと馬券検討に集中し、他場のレースも含めて一日中競馬を楽しみたいという、いわゆる「馬券派」の玄人ファンにとって、これ以上ないほどコストパフォーマンスに優れた最適な席と言えるでしょう。
平日開催の指定席
- YUKINOSUKE
「平日開催」と聞くと、多くの方が月曜日の祝日(いわゆる3日間開催)を想像されるかもしれませんが、ここで主に解説するのは、それとは異なるイレギュラーなケースです。JRAの競馬開催は、カレンダー通りであれば基本的に土曜日と日曜日、および一部の祝日(敬老の日、成人の日など)に行われます。
これら以外の、いわゆるカレンダー上の「平日」(火曜日~金曜日)に開催が行われることは非常に稀です。こうした事態は、主に台風の接近や、予期せぬ大雪といった深刻な天候不順によって、予定されていた土日の開催が中止・順延となった場合の「代替開催」として発生します。
では、もしG1レースが日曜から火曜日に順延した場合、指定席はどのように扱われるのでしょうか。
代替開催日の指定席は「新規に再販売」される
まず大前提として、中止となった日(例:日曜日)の指定席券は、天候不順が理由であっても原則としてすべて「払い戻し」の対象となります。その指定席券が、そのまま代替開催日(例:火曜日)にスライドして使えるわけではないため、厳重な注意が必要です。
そして、代替開催日(火曜日)の指定席は、改めてJRAのネット予約サイトで「新規に(再)販売」されます。この販売スケジュール(例:前日の月曜日から先着順で販売開始など)は、開催の可否とあわせてJRA公式サイトで直前に発表されるため、こまめな情報確認が必須となります。
平日開催(代替)の指定席倍率とメリット
ここからが本題ですが、この「平日代替開催」の指定席倍率は、通常のG1開催日とは比較にならないほど著しく低くなります。その理由は単純明快で、「平日(火~金)は仕事や学校があり、物理的に来場できる人が激減する」ためです。
G1レース(例えば、天皇賞(春))が平日に順延したとしても、需要(来場できる人数)が供給(席数)を大きく下回る可能性が高くなります。そのため、抽選は行われず、前日などから「先着順販売」となるケースがほとんどです。
これは、抽選に外れ続けているファンにとっては、またとないチャンスとも言えます。普段は倍率100倍近くになるようなLソファやペアテーブル、あるいはゴール前のA指定席といった最上級の席ですら、この平日代替開催日に限っては、驚くほど容易に(場合によっては定員割れで)確保できる可能性が非常に高いのです。
もし平日に急遽休みを取ることが可能であれば、G1レースを最高の席で観戦できる、またとない「穴場」的な機会となるかもしれません。
京都競馬場の平日の利用に関しては、こちらの記事京都競馬場、平日は何ができる?完全ガイドで詳しく解説しています。
「月曜祝日開催(3日間開催)」との違い
最後に、この記事の冒頭で触れた「月曜祝日開催」について再度注意喚起します。敬老の日や成人の日など、カレンダー上であらかじめ設定されている「3日間開催」の最終日(月曜日)は、本稿で解説した「平日代替開催」とはまったく異なります。
これは「平日」ではなく「休日」です。したがって、G1レースが開催されていなくても、通常の土日開催と同等か、あるいは休日最終日として行楽需要が高まり、むしろ通常より混雑する可能性もあります。当然、指定席の需要も高く、倍率が低くなることは期待できません。この二つのケースを混同しないよう、十分にご注意ください。
京都競馬場指定席の倍率を総括
- YUKINOSUKE
最後に、この記事で解説してきた「京都競馬場 指定席 倍率」に関する重要なポイントを、G1観戦を目指す方のために要点としてまとめます。観戦計画を立てる際のチェックリストとしてご活用ください。
- 京都競馬場の指定席倍率は、G1開催日に限り極端に高騰する傾向にある
- 特に「天皇賞(春)」と「菊花賞」は、京都で開催されるG1の中でも最も高い水準の倍率に達する
- Lソファやペアテーブルといったグループ席は、元々の席数が少ないため倍率100倍近くと当選は極めて困難
- ゴール前のA指定席やB指定席といった伝統的な人気席も、G1当日は約10倍の高難易度
- G1以外の通常開催日(平場開催)であれば、指定席の倍率は大幅に下がり、先着販売で容易に確保できることも多い
- 抽選の当選確率を上げる最も有効かつ現実的な方法は、JRAカード会員になること
- JRAカード会員は「先行抽選」への参加資格を得られ、一般会員より抽選チャンスが1回増える
- 同行者がいる場合、申込者と同行者を入れ替えて申し込むことで、抽選の口数を物理的に増やせる
- 指定席の抽選に外れても、「入場券」さえあれば競馬場への入場自体は可能
- ただしG1当日は、安全確保のため「入場券の当日現金発売」が中止され、事前の「入場券ネット予約」が必須となる可能性が非常に高い
- 競馬場窓口での指定席当日発売は原則廃止されており、現在はネット予約の「残席販売(先着順)」が基本
- スマートシートは最も安価で臨場感を味わえるが、天候の影響を直接受ける屋外席である
- 雨天時にスマートシートを選ぶ際は、屋根が深い3階の「さ」列より後方の席が比較的濡れにくい
- プライベートシートは快適な屋内ブース席だが、自分の席からコースは一切見えないという最大の注意点がある
- プライベートシートは、眺望よりも快適な環境で馬券検討に集中したい人向けの、コストパフォーマンスに優れた席である
また宿泊を検討される方には、こちらの記事京都競馬場のホテル完全ガイド!淀駅周辺とアクセス重視の宿泊戦略も参考になると思いますので、合わせてお読み下さい。
















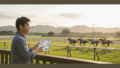
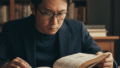
コメント