競馬のレースで予想が見事に的中したにもかかわらず、「なぜか手元の資金が増えていない…」「むしろ、少し減っている気がする…」といった、喜ぶに喜べない、少しほろ苦い経験をお持ちではないでしょうか。競馬ファンの間では当たり前のように使われる「トリガミ」という言葉。この記事では、そんな競馬の永遠の課題とも言える現象について、その基本的な意味の解説から、具体的な防止策、さらには一歩進んだ戦略的な思考法に至るまで、網羅的に、そして深く掘り下げて解説していきます。
もちろん、単に「トリガミとは何か」という言葉の意味を説明するだけにとどまりません。その意外な由来や文化的背景から、プロの馬券師たちが実践する、時には戦略的に「トリガミは悪くない」とされる高度な視点についても詳しくご紹介します。また、中央競馬とは異なる注意点が必要な地方競馬特有のトリガミ事情や、多くのファンが見落としがちですが、後々大きな問題になりかねない競馬の払戻金と税金の関係性にも光を当てていきます。この記事を最後までお読みいただくことで、あなたの馬券購入における「なぜか儲からない」という長年の悩みに、明確な答えを提示します。
さらに、どうすればトリガミを効果的に防止できるのか、そして「トリガミにならない買い方」は存在するのか、という核心的な疑問に対し、具体的なテクニックを交えて回答します。長期的に利益を上げ続けている「競馬で勝ってる人」の買い方の特徴を分析し、巷で囁かれる「競馬で必ず儲かる買い方」というものの本質的な考え方を理解することで、単なる知識として終わらせず、明日からの馬券購入にすぐに活かせる実践的なノウハウとしてお持ち帰りいただけることでしょう。感覚的な馬券購入から脱却し、論理的な資金管理に基づいた、新しい競馬の楽しみ方を発見する第一歩として、ぜひ本記事をお役立てください。
- トリガミの基本的な意味と語源
- トリガミを防止するための具体的な買い方
- トリガミと税金の関係性
- 長期的な回収率を高めるための考え方
競馬のトリガミに関する基礎知識
- まずトリガミとは何かを解説
- トリガミの由来となった意外な言葉
- 戦略的にトリガミは悪くないのか?
- 地方競馬のトリガミで注意すべき点
- 競馬のトリガミと税金の関係性
まずトリガミとは何かを解説
- YUKINOSUKE
競馬のレースで予想が見事に的中したはずなのに、払戻機の前で表示された金額を見て首を傾げた経験、あるいはインターネット投票の残高が思ったように増えていない、という経験はないでしょうか。この、的中した喜びと同時に訪れる不可解な資金減少の正体こそが、競馬を楽しむ上で避けては通れない「トリガミ」という現象です。
口語では「ガミる」や「ガミった」とも表現されますが、その定義は極めて明確です。競馬におけるトリガミとは、馬券が的中したにもかかわらず、そのレースでの払戻金が馬券の総購入金額を下回り、結果的に収支がマイナスになってしまう状態を指します。せっかく多大な時間と労力をかけて予想を的中させたにもかかわらず、なぜこのような残念な事態が起こるのでしょうか。そのメカニズムは、主に3つの原因に集約されます。
原因1:買い目点数の過剰な増加
最も一般的で、多くの競馬ファンが陥りがちな原因が、買い目点数の増やしすぎです。レースが近づくにつれて、「本命馬は堅いが、相手が絞りきれない」「万が一のために、この穴馬も抑えておきたい」といった不安や欲から、保険のつもりで買い目を次々と追加してしまう心理が働きます。結果として、的中率は上がりますが、一点一点の的中に賭けられる金額は薄まり、的中時の払戻金が膨れ上がった総投資額に追いつかなくなってしまうのです。
原因2:人気サイドでの「堅い」決着
たとえ買い目点数を絞っていたとしても、レース結果が多くの人の予想通り、1番人気と2番人気の組み合わせといった「堅い」内容で決着した場合にもトリガミは発生しやすくなります。競馬のオッズは、簡単に言えば馬券の支持率であり、多くの人が買う組み合わせほどオッズは低くなります。そのため、人気サイドの決着では、そもそも払戻金の倍率が低く設定されており、数点の組み合わせを購入しただけでも、払戻金が購入総額を下回ってしまうケースが起こり得るのです。
原因3:レース直前のオッズ変動
見落とされがちですが、意図せぬトリガミを引き起こす要因として、レース直前のオッズ変動、いわゆる「オッズ割れ」も挙げられます。例えば、前日に馬券を購入した時点では、どの組み合わせが的中してもプラス収支になる計算だったとします。しかし、レース当日に特定の馬券に人気が集中してオッズが大幅に下がった結果、購入時点では想定していなかったトリガミの組み合わせが発生してしまうことがあるのです。これは、オッズが確定する締め切り直前まで人気の動向を注視していない場合に陥りやすい罠と言えるでしょう。
シミュレーションで見るトリガミの発生例
ここで、具体的な買い方とレース結果を想定して、トリガミがどのように発生するのかをシミュレーションしてみましょう。
| 券種 | 購入内容 | 総購入額 | 的中組み合わせ | 的中オッズ | 払戻金 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3連複 | 5頭ボックス(10点)を各100円 | 1,000円 | 人気サイドで決着 | 7.5倍 | 750円 | -250円 |
| ワイド | 人気馬から3頭へ流し(3点)を各500円 | 1,500円 | 最も堅い組み合わせで決着 | 2.1倍 | 1,050円 | -450円 |
上の表のように、買い目を広げた場合や、人気サイドを厚めに買った場合にトリガミが発生しやすいことが分かります。
このようにして発生するトリガミは、単なる金銭的な損失だけでなく、「的中したのに損をした」という複雑な精神的ダメージをもたらします。この悔しさが冷静な判断を狂わせ、次のレースで損失を取り返そうと無謀な大穴狙いに走らせるなど、さらなる負けのスパイラルに繋がる危険性もはらんでいます。
だからこそ、競馬で安定した利益を目指すためには、ただ単にレースを的中させる技術だけでなく、このトリガミという現象を正しく理解し、それをいかに計画的に回避するかという、高度な資金管理の視点が極めて重要な課題となるのです。
トリガミの由来となった意外な言葉
- YUKINOSUKE
「トリガミ」という、一度聞いたら忘れない独特な響きの言葉。カタカナで表記されることもあり、比較的新しい現代的な造語や、競馬ファンの間で自然発生した俗語の一種だと思っている方も少なくないかもしれません。しかし、そのルーツを辿っていくと、意外にも江戸時代の町人文化や、そこに生きた人々の価値観にまで遡ることができるのです。
現在、トリガミの語源として最も有力視されているのが、「粋(いき)が身を食う」という古くからのことわざです。
このことわざは、主に江戸時代後期、町人文化が爛熟した頃に使われ始めたとされています。ここで言う「粋」とは、単にお洒落という意味合いだけではありません。金銭に執着しないさっぱりとした気性や、遊びの道の酸いも甘いも噛み分けた、洗練された振る舞いなどを指す、当時の江戸町人が理想とした美意識の一つでした。しかし、ことわざが示す通り、その「粋」を追求するあまり、花柳界などの遊びにのめり込みすぎて散財し、最終的には財産を失い身を滅ぼしてしまう、という教訓や戒めを含んだ意味合いを持っています。
ことわざから競馬用語への変遷
この「身を滅ぼす」、つまり「損をする」という部分が、時代の流れと共に俗語化していきます。「身(み)を食う」が、より語呂の良い「ガミを食う」という隠語的な表現へと音が変化(転訛)していったと考えられています。そして、この「ガミを食う」という言葉が、競馬の世界で馬券を「取る(的中させる)」という行為と結びついたのです。
つまり、「馬券を取った(的中した)にもかかわらず、ガミを食った(損をした)」という、まさに競馬における皮肉な状況を的確に表現した言葉として、「トリガミ」が誕生し、定着していったと言われています。
なぜ他の公営競技でも使われるのか?
ちなみに、この「トリガミ」という言葉は競馬だけの専門用語ではありません。競輪、競艇、オートレースといった他の公営競技でも、全く同じ意味を持つ共通の俗語として広く使われています。
その背景には、これらの競技がすべて「パリミュチュエル方式」という投票券の販売方法を採用していることがあります。これは、参加者全体の投票金額(売上)から、主催者が一定の割合を手数料(控除率)として差し引き、残りの金額を的中者で分配する仕組みです。この仕組みがあるからこそ、的中者が多すぎる(人気サイドで決着する)と一人当たりの配当が少なくなり、「的中しても購入額を下回る」というトリガ-ミ現象が発生し得るのです。
単なるギャンブル用語と思いきや、その一つの言葉の裏には、江戸時代の美意識、言葉の音の変化、そして公営競技が持つ共通の仕組みという、複数の文化的・歴史的・制度的な背景が凝縮されています。次に競馬場で「ガミったー」という声を聞いたとき、その言葉の裏にある深い歴史に思いを馳せてみるのも一興かもしれませんね。
戦略的にトリガミは悪くないのか?
- YUKINOSUKE
競馬ファンの間では「トリガミは絶対に避けるべき悪」という認識が一般的です。的中したにもかかわらず資金が減るという事実は、直感的に受け入れがたいものでしょう。しかし、競馬で長期的に利益を上げている、いわゆる「勝ち組」と呼ばれる人々は、このトリガミという現象を単なる悪とは決めつけず、むしろ自身の馬券戦略の中に巧みに組み込んでいることがあります。より高度な馬券戦略の観点から見ると、すべてのトリガミが悪いものではなく、計画的・戦略的な「良いトリガミ」は、むしろ受け入れるべきだという考え方も存在するのです。
これは、トリガミが時に「保険」や「リスクヘッジ」として、極めて有効な役割を果たすことがあるためです。競馬で大きな利益を狙うには、高配当が期待できる穴馬を狙う「攻め」の姿勢が不可欠ですが、攻めの姿勢は常に不的中のリスクと隣り合わせです。そこで重要になるのが、本線の攻めの馬券が外れた場合に備える「守り」の馬券。この守りの馬券が結果的にトリガミになったとしても、それは計画通りのリスク管理と言えるでしょう。
シナリオで理解する「良いトリガミ」の構造
言葉だけでは分かりにくいかもしれませんので、具体的なレースシナリオを想定して、「良いトリガミ」がどのように機能するのかを見てみましょう。
設定:1番人気が少し抜けているが、2着以下は混戦模様で波乱も考えられるG2レース。あなたの本命は、前走の内容が良くオッズ妙味のある5番人気の馬だとします。総投資金額は5,000円です。
| 馬券の種類 | 購入内容 | 投資金額 | 狙い |
|---|---|---|---|
| 本線(攻め) | 5番人気から、相手に8, 10, 12番人気の穴馬への馬連流し(3点) | 各1,000円(計3,000円) | 穴馬が絡んだ場合の高配当を狙う。 |
| 抑え(守り) | 5番人気から、相手に1, 2番人気の人気馬へのワイド流し(2点) | 各1,000円(計2,000円) | 本命馬は来るが相手が人気馬だった場合の損失を最小限に抑える。 |
レース結果:あなたの読み通り5番人気の馬は2着に好走しましたが、1着は1番人気の馬でした。
この場合、本線の馬連は不的中ですが、抑えのワイド馬券(5番人気 – 1番人気)が的中します。このワイドのオッズが4.5倍だったとすると、払戻金は1,000円 × 4.5倍 = 4,500円。総投資金額は5,000円なので、結果は500円のトリガミとなります。
一見すると500円の損ですが、もし抑えの馬券を購入していなければ、5,000円が全額不的中となっていたところでした。しかし、計画的な抑え馬券によって、損失をわずか500円にまで圧縮できたのです。これは紛れもなく「戦略的で価値のあるトリガミ」と言えるでしょう。このように、投資した資金が全額失われる最悪のシナリオを回避し、次のレースへ挑戦するための軍資金を確保することが、戦略的トリガミの最大のメリットです。
注意すべき「悪いトリガミ」とは
一方で、明確な戦略や意図がなく、ただ「当てたい」という気持ちだけで無計画に買い目を広げた結果生じる損失は、「悪いトリガミ」に他なりません。例えば、以下のような買い方は「悪いトリガミ」の典型例です。
- 人気馬のボックス買い:不安だからと1番人気から5番人気までの馬連ボックス(10点)などを均等に購入する。どの組み合わせで決着しても、ほとんどがトリガミか、ごくわずかな利益にしかならない可能性が非常に高い買い方です。
- 複勝の多点買い:「とにかく当てたい」という理由で、複勝を3点、4点と購入する。1番人気の複勝オッズは1.1倍〜1.3倍程度であることが多く、複数点が的中したとしても、購入総額を上回ることは極めて稀です。
トリガミの常態化は危険信号
前述の通り、もしあなたの馬券収支で意図しないトリガミが続いている場合、それは買い目点数がご自身の戦略以上に多いか、オッズの低い馬券ばかりを無意識に選んでいる証拠です。これは資金管理の観点から極めて危険なサインであり、馬券の組み立て方そのものを根本から見直す必要があるでしょう。
このように、トリガミは一概に「悪」と切り捨てるのではなく、その一回一回が、自身の馬券戦略の中でどのような意味を持つのか(計画的なリスクヘッジなのか、無計画な損失なのか)を正しく見極めた上で、上手に付き合っていくことが求められるのです。
地方競馬のトリガミで注意すべき点
- YUKINOSUKE
全国各地の競馬場で開催され、地域に根差した魅力を持つ地方競馬ですが、馬券戦略を立てる上では、中央競馬とは異なるいくつかの重要な特徴を理解しておく必要があります。特にトリガミという観点においては、中央競馬と比較して地方競馬は構造的に発生しやすい傾向があるため、同じ感覚で馬券を購入していると、意図せぬ損失を被る可能性が高まります。
その最大の理由は、元の文章でも触れられている通り、1レースあたりの平均出走頭数が少ないという点にあります。しかし、理由はそれだけにとどまりません。コース形態やレース体系といった、地方競馬ならではの複数の要因が複合的に絡み合い、結果として「配当が低くなりやすい=トリガミになりやすい」環境を生み出しているのです。
要因1:出走頭数の少なさがもたらす数学的な不利
まず基本として、出走頭数が少なくなると、組み合わせの総数が劇的に減少します。これは馬券の的中しやすさに直結する一方で、配当の妙味を大きく損なう原因となります。例えば、馬券の王道とも言える3連単で、その組み合わせ総数がどれほど違うかを見てみましょう。
出走頭数による3連単の組み合わせ総数
| 出走頭数 | 組み合わせ総数 | 備考 |
|---|---|---|
| 18頭 | 4,896通り | 中央競馬のG1レースなど、フルゲートの場合 |
| 12頭 | 1,320通り | 地方・中央の一般的なレース |
| 8頭 | 336通り | 地方競馬で頻繁に見られる少頭数レース |
このように、8頭立てのレースは18頭立てに比べて組み合わせが14分の1以下しかありません。当然、的中はしやすくなりますが、人気サイドで決着した際の配当は極めて低くなります。このような数学的な土台の上で、中央競馬と同じ感覚で5頭ボックス(10点)のような買い方をしてしまうと、たとえ的中してもトリガミになる可能性が非常に高くなるのです。
要因2:コース形態とレース体系が生む「堅い決着」
出走頭数に加えて、地方競馬のレースが「堅い決着」、つまり人気馬同士で決まりやすい背景には、以下のような特徴も影響しています。
- 小回りで直線の短いコース形態:多くの地方競馬場は中央競馬に比べてコースが小回りで、最後の直線も短い傾向にあります。これにより、後方からの追い込みが決まりにくく、先行した能力上位の馬がそのまま有利にレースを進めやすくなります。結果として、レース展開の「紛れ」が少なくなり、順当な結果に終わりやすいのです。
- 騎手のリーディング固定化:各地方競馬場では、その競馬場を専門とするトップ騎手と、それ以外の騎手との間に、中央競馬以上にはっきりとした実力差や信頼度の差が存在することが少なくありません。そのため、トップ騎手が騎乗する馬に人気が過剰に集中し、オッズがさらに低くなるという現象が起こりがちです。
地方競馬で勝つためのトリガミ対策
これらの構造的な特徴を踏まえた上で、地方競馬でトリガミを避け、収支を向上させるためには、中央競馬以上に意識的な戦略の切り替えが求められます。
- レース選びを徹底する:まず、出走頭数が10頭以下のレースでは、高配当を狙うこと自体が難しいと認識しましょう。このようなレースでは、無理に多点買いで勝負するのではなく、確信が持てる1頭の単勝・複勝で堅実に勝負するか、思い切って「見(けん)」をする勇気が重要です。
- ボックス買いを封印する:地方競馬の少頭数レースにおいて、安易なボックス買いはトリガミへの直行便とも言えます。必ず軸馬を1頭、もしくは2頭に定め、そこから相手へ流す「フォーメーション」や「流し」といった買い方を徹底し、無駄な買い目を1点でも多く削る努力をしましょう。
- 券種を工夫する:3連単のような高難度の券種に固執せず、馬連やワイドといった、より少ない点数で勝負できる券種を中心に考えるのも有効な戦略です。特にワイドは、人気薄の馬を1頭絡めるだけで、堅い決着の中でもトリガミを避けつつ利益を確保できる可能性があります。
地方競馬を楽しまれる方は、こうした中央競馬との構造的な違いをしっかり認識することが大切です。そして、その日のレース条件に合わせて、柔軟に買い方を最適化していくことこそが、トリガミという罠を回避し、競馬をより深く楽しむための鍵となるでしょう。
地方競馬に関しては、地方競馬のオッズが低い理由とは?勝率を上げる攻略法を解説でも詳しく解説しています。
競馬のトリガミと税金の関係性
- YUKINOSUKE
競馬を楽しむ上で、ほとんどのファンが「高額配当を当てた人の話」や「自分には関係ない遠い話」として捉えがちなのが、税金の問題ではないでしょうか。しかし、「トリガミで損をしているのに、さらに税金まで支払う必要があるのか?」という素朴な疑問は、馬券を購入するすべての人にとって、実は非常に重要な知識となります。
日本の税法上、競馬の払戻金は原則として「一時所得」として分類され、年間の利益が一定額を超えた場合には課税対象となり、確定申告が必要になります。そして、ここでの核心は、たとえレース単位の収支がマイナスとなるトリガミであっても、その的中によって得た払戻金は、税金の計算上、課税対象となりうる「収入」として計上しなければならない、という厳然たるルールが存在する点です。
年間収支モデルで見る一時所得の計算
言葉だけでは非常に分かりにくいため、ある競馬ファンの一年間の収支をモデルケースとして、一時所得がどのように計算されるのかを具体的に見ていきましょう。
【Aさんの年間収支モデル】
| レース | 総購入額 | 結果 | 払戻金(収入) | 当たり馬券の購入費(経費) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有馬記念 | 10,000円 | 的中 | 150,000円 | 1,000円 | 100円×100点の購入 |
| 日本ダービー | 5,000円 | 的中(トリガミ) | 4,000円 | 1,000円 | 収支は-1,000円 |
| その他のレース | 485,000円 | 不的中 | 0円 | 0円 | 年間のハズレ馬券合計 |
| 年間合計 | 500,000円 | – | 154,000円 | 2,000円 | 年間の収支は-346,000円 |
上の表のように、Aさんは年間を通じて見ると346,000円のマイナス収支です。しかし、税金の計算はこれとは全く異なります。一時所得の計算式に当てはめてみましょう。
- 総収入金額を計算する:
150,000円(有馬記念) + 4,000円(日本ダービー) = 154,000円
※トリガミだった日本ダービーの払戻金も、収入として合算されます。 - 収入を得るための支出額(経費)を計算する:
1,000円(有馬記念の当たり馬券) + 1,000円(日本ダービーの当たり馬券) = 2,000円
※年間のハズレ馬券代498,000円は、経費には一切含まれません。 - 課税対象となる一時所得を計算する:
154,000円(総収入) – 2,000円(経費) – 500,000円(特別控除額) = -348,000円
※計算結果がマイナスなので、このケースでは課税対象となる所得はなく、確定申告の必要もありません。
この計算から分かる通り、年間の払戻金合計が特別控除額の50万円を超えない限り、ほとんどの場合で納税の義務は発生しません。しかし、もしAさんの有馬記念の払戻金が100万円だったとすれば、課税所得が発生し、確定申告が必要になるのです。
「ハズレ馬券は経費にならない」は絶対か?
前述の通り、ハズレ馬券は経費にならないのが大原則です。しかし、過去の最高裁判所の判例(平成29年)において、極めて例外的なケースとして、ハズレ馬券代が経費として認められ、払戻金が「雑所得」に区分された事例があります。ただし、これはソフトウェアを利用して年間数億円規模の馬券を営利目的で継続的に購入していた特殊なケースであり、趣味の範囲で競馬を楽しむほとんどの一般ファンには当てはまりません。安易に「自分も雑所得にできる」と考えるのは非常に危険です。
税金に関する極めて重要な注意点と相談先
競馬の税金に関するルールは複雑であり、個々の所得状況によって扱いが異なります。もし高額の払戻金を得た場合、ご自身の判断で「申告しなくても大丈夫だろう」と放置してしまうと、後日税務署からの指摘を受け、本来の税額に加えて延滞税や無申告加算税といった重いペナルティが課される可能性があります。正確な情報とご自身の納税義務については、必ず国税庁のウェブサイト(参照:タックスアンサー「No.1490 一時所得」)を確認するか、お近くの税務署または税理士などの専門家へ速やかにご相談ください。
「トリガミだから税金は関係ない」という考えは、時に大きなリスクを伴う誤解です。競馬を健全に長く楽しむためにも、正しい税金の知識を身につけておくことは、すべての競馬ファンにとっての責務と言えるでしょう。
競馬の税金に関しては、競馬の税金、バレないは嘘!申告しないとどうなるでも詳しく解説しています。
競馬のトリガミを防止する買い方
- 競馬のトリガミを防止する3つのコツ
- 具体的にトリガミにならない買い方は?
- 競馬で勝ってる人の買い方を参考にする
- 競馬で必ず儲かる買い方という考え方
- 競馬のトリガミを理解して収支改善へ
競馬のトリガミを防止する3つのコツ
- YUKINOSUKE
意図しないトリガミを計画的に防ぎ、競馬の収支を長期的に安定・向上させるためには、単なる予想の技術だけでなく、馬券購入の際に意識すべきいくつかの重要な原則が存在します。これらは、初心者からベテランまで誰もが実践できる、馬券との付き合い方を根本から改善するための思考法です。ここでは、特に重要な3つのポイントを、具体的な実践方法を交えながら深掘りして紹介します。
1. 買い目を絞る(選択と集中の原則)
最もシンプルかつ絶大な効果を持つトリガミ防止策は、勇気を持って買い目点数を減らす、すなわち「選択と集中」を実践することです。前述の通り、トリガミが発生する最大の原因は、的中を逃すことへの不安(ロスアバージョン)からくる点数の増やしすぎにあります。保険のつもりでアレもコレもと馬券を買い足していく行為は、一見するとリスクを分散しているように見えますが、実際には利益を分散させているに他なりません。結果として、的中しても利益が出ない、あるいはごくわずかという本末転倒な事態に陥りがちです。
これを防ぐためには、馬券を一枚追加するごとに、自問自答する習慣をつけることが有効です。「この買い目は、自分の予想の根幹をなす本命筋なのか、それとも単なる不安からくる気休めの保険なのか?」と問いかけ、後者であるならば思い切って削る決断が求められます。「万が一」を考えすぎず、自分の予想と心中するくらいの気持ちで、自信のある組み合わせに投資を集中させることが、結果として回収率を高める最短ルートとなるでしょう。
2. オッズを確認してシミュレーションする(購入前の出口戦略)
馬券の購入ボタンを押す前の一瞬の作業が、トリガミを回避する上で決定的な差を生みます。それは、購入する馬券の組み合わせとオッズを基に、「どの組み合わせで的中しても、必ずプラス収支になるか」を事前に計算(シミュレーション)する習慣です。
特に複数の組み合わせを購入する場合、その中で最もオッズが低い(最も堅い)組み合わせが的中した場合でも、しっかりと利益が出るか(=ガミらないか)を計算することが極めて大切です。この、購入する馬券全体の期待払戻率の最低ラインを「合成オッズ」と呼び、この数値が総投資金額を上回っているかを確認する作業は、いわば投資における「出口戦略」を立てることに等しいのです。
購入直前!トリガミ回避のための3ステップ確認法
- 最終的な買い目と総投資額を確定させる:まず、購入したいすべての馬券と、1点あたりの金額を決め、総投資額を算出します。
- 最低オッズの組み合わせを確認する:購入予定の買い目の中で、最も払戻倍率が低い組み合わせを見つけ出します。
- 払戻額と総投資額を比較する:その最低オッズで的中した場合の払戻額を計算し、総投資額を上回っているかを確認します。もし下回っている(トリガミになる)場合は、点数を削るか、購入を見送るかの判断が必要です。
現在、多くのインターネット投票サイトでは、購入前に各組み合わせの想定払戻金が一覧で表示されます。この機能を最大限に活用し、購入前に必ず指差し確認するくらいの意識を持ちましょう。
3. 期待値に応じて資金配分を変える(強弱をつける投資術)
全ての買い目を画一的に同じ金額で購入する「均等買い」は、初心者にも分かりやすい方法ですが、トリガミを誘発しやすいという欠点もはらんでいます。より戦略的にトリガミを回避するためには、自身の予想の自信度やオッズ(期待値)に応じて、投資金額に強弱をつける「傾斜配分」というテクニックが非常に有効です。
例えば、総投資金額を3,000円と定め、以下の3点の馬連を購入するとします。
| 買い方 | 組み合わせA(5.0倍) | 組み合わせB(10.0倍) | 組み合わせC(20.0倍) | 総投資額 | A的中時の収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均等買い | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 | +2,000円 |
| 傾斜配分 | 1,800円 | 900円 | 300円 | 3,000円 | +6,000円 |
上の表のように、同じ3,000円の投資でも、資金配分を変えるだけで結果は大きく変わります。均等買いの場合、最も可能性の高い組み合わせAが的中しても利益は2,000円です。一方、傾斜配分では、最も的中しやすい組み合わせAに厚く資金を投下することで、的中時のリターンを最大化し、6,000円の利益を確保できます。さらに、この配分であれば、どの組み合わせが的中してもトリガミになることはありません。
このように、自分の予想の核となる買い目に資金を集中させることで、トリガミのリスクを抑えつつ、的中時のリターンを最大化するという、リスクとリターンのバランスが取れた、より戦略的な馬券構成が可能になるのです。
具体的にトリガミにならない買い方は?
- YUKINOSUKE
前項で解説したトリガミ防止の3つのコツは、馬券購入における重要な「原則」です。しかし、その原則を実際の馬券に落とし込むためには、券種の選び方や馬券の組み立て方といった、より具体的な「戦術」が必要不可欠となります。ここでは、トリガミのリスクを物理的に減らし、かつ戦略的な利益を狙うための、具体的な馬券の買い方をいくつか深掘りして紹介します。ご自身の競馬スタイルや、そのレースの特性に合わせて使い分けることで、あなたの馬券戦略の引き出しは格段に増えることでしょう。
単勝・複勝の1点買い(原点にして究極の守り)
全ての馬券術の原点にして、トリガミという概念が絶対に発生しない唯一の方法、それが単勝または複勝の1点買いです。選んだ馬は1頭、買い目も1点なので、的中すれば払戻率(JRAの場合、単勝・複勝ともに通常1.1倍以上)に従って、必ず購入金額を上回る払戻金が得られます。そのシンプルさゆえに、予想の精度がダイレクトに結果に反映され、ごまかしが一切効きません。
もちろん、数多くの出走馬の中からたった1頭の勝ち馬(もしくは3着以内に入る馬)を選び抜くという、予想そのものの難しさはあります。また、特に複勝では的中しても大きなリターンは期待しにくいでしょう。しかし、「今日の最終レースは絶対に負けられない」「長い不調から脱出するきっかけとして、まずは的中感覚を取り戻したい」といった状況において、この買い方は最強の「守りの戦術」として機能します。
注意:複勝の多点買いはトリガミの罠
「的中しやすいから」という理由で、複勝を2点、3点と購入するのは非常に危険な行為です。1番人気の複勝オッズは1.1倍〜1.3倍程度であることが多く、たとえ2点が的中したとしても、購入総額を上回るケースは稀です。複勝の多点買いは、トリガミのリスクを自ら積極的に作り出しにいく行為に他ならないと心得ましょう。
軸馬を決めて流すフォーメーション(無駄を削る知性の戦術)
前述の通り、3連複や3連単といった券種は、少し欲張って手広く構えると、あっという間に買い目点数が増えてしまいます。こうした券種でトリガミを避けつつ利益を狙う際に、極めて有効な武器となるのが「フォーメーション」という買い方です。
「フォーメーション」に関しては、こちらの記事【フォーメーションをわかりやすく解説!買い方のコツ】で詳しく解説しています。
これは、選んだ馬の全ての組み合わせを購入する「ボックス」とは異なり、1着、2着、3着に来る馬の候補をそれぞれ個別に指定することで、自分の予想の確信度に応じて無駄な買い目を大幅に削減できる、知的な買い方です。
買い方の工夫による点数比較(3連単・5頭選択のケース)
例えば、5頭(①,②,③,④,⑤)に可能性があると判断し、中でも①の馬への信頼が厚い場合で比較してみましょう。
| 買い方 | 買い方の例 | 合計点数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ボックス買い | ①,②,③,④,⑤の5頭ボックス | 60点 | どの3頭がどの順番で来ても的中するが、点数が膨大でトリガミのリスクが極めて高い。 |
| フォーメーション | 1着:① 2着:②,③ 3着:②,③,④,⑤ |
6点 | 1着が①、2着が②か③であることが前提。予想がハマれば、投資を10分の1に抑えられる。 |
このように、軸馬やレース展開に自信がある場合は、フォーメーションを駆使することで投資金額を劇的に削減し、トリガミのリスクを軽減させることが可能です。一方で、似たような買い方に「マルチ」がありますが、これは軸馬を決めた後に1着〜3着の着順を問わないようにするもので、点数が3倍〜6倍に膨れ上がるため、トリガミの温床になりやすい点には注意が必要です。
人気馬と穴馬を組み合わせる(回収率向上のための攻防一体戦術)
トリガミの直接的な原因である、オッズの低い人気馬同士の組み合わせを意識的に避けること。これは、トリガミ防止と同時に、長期的な回収率向上を目指す上で最も重要な考え方の一つです。その具体的な実践方法が、人気馬と穴馬(人気薄の馬)を組み合わせるという、攻防一体の戦術になります。
なぜこの組み合わせが有効なのでしょうか。それは、競馬のオッズが必ずしも馬の実力を正確に反映しているわけではないからです。一般的に、人気馬は多くのファンが購入するため実力以上にオッズが低くなりがち(過剰人気)で、逆に人気薄の馬は実力以下に見られオッズが高くなりがち(過小評価)という歪みが生じます。このオッズの歪みを突くことこそが、期待値の高い馬券術の基本であり、その最も分かりやすい形が「人気馬+穴馬」の組み合わせなのです。
「人気馬+穴馬」の具体的な馬券構成例
- 馬連・ワイドでの実践:軸馬は1〜3番人気の中から1頭選び、相手は6番人気以下の馬の中から数頭選んで流す。
- 3連複での実践:フォーメーションを活用し、「1頭目(軸):1〜2番人気」「2頭目:3〜5番人気」「3頭目:6番人気以下の穴馬」といった形で、人気順にフィルターをかけて組み合わせる。
もちろん、人気薄の馬が馬券に絡む確率は低いため、この戦術は短期的に見れば不的中が続くこともあります。しかし、的中した時のリターンは非常に大きく、一回の的中で多くの負けを取り返せるだけの破壊力を秘めています。短期的な的中率に一喜一憂せず、長期的な回収率を追い求めるという強い意志を持って取り組むべき戦術と言えるでしょう。
馬券の買い方に関しては、こちらの記事【競馬で回収率100%を超える買い方をプロが徹底解説】でも詳しく解説しています。
競馬で勝ってる人の買い方を参考にする
- YUKINOSUKE
競馬の世界には、残念ながら大多数の「負け組」と、ごく一握りの「勝ち組」が存在します。俗に「勝ち組」と呼ばれる、長期的に競馬でプラス収支を維持している人たちと、そうでない人たちとを分ける決定的な違いは、果たして何なのでしょうか。それは、単なるレース展開や馬の能力を見抜く予想の巧みさだけではありません。むしろ、それ以上に重要となるのが、感情を排した「馬券との向き合い方」、すなわち、徹底した自己規律と資金管理の哲学に基づいています。
彼らは目先の1レースの的中に一喜一憂することなく、常に「的中率」と「回収率」という2つの重要な指標のバランスを冷静に見極めています。そして、どうすれば月単位・年単位で資産を増やせるかという、ある種の事業や投資に近い視点で競馬と向き合っているのです。ここでは、そんな彼らに共通する4つの思考法と行動原則を深掘りしていきます。
1. レース選びを厳選する(自分の土俵で戦う)
勝ち組に共通する第一の原則は、「勝てるレースでしか勝負しない」というものです。中央競馬だけでも、土日で最大72レースが開催されますが、彼らはその全てに手を出すようなことは決してしません。人間の集中力や分析能力には限界があり、全てのレースを同レベルの熱量で分析することは不可能です。むやみに手を広げれば、一レースあたりの分析の質は必然的に低下し、結果として期待値の低い、勝つべくして勝てない馬券を買うことになってしまいます。
だからこそ彼らは、自身の過去の馬券成績をデータとして記録・分析し、「東京競馬場の芝1600m」「2勝クラスのダート短距離戦」といった、自分の得意な条件、いわば「自分の土俵」を客観的に把握しています。そして、その得意な条件のレースが現れるまでじっと待ち、勝機が訪れた時にのみ、集中して資金を投下するのです。
2. 破れないルールを持つ(資金管理の徹底)
人間は、利益を得る喜びよりも損失を被る苦痛を強く感じるようにできています。そのため、負けが込んでくると、冷静さを失い「次で取り返そう」と無謀な大勝負に出てしまいがちです。勝ち組は、この人間心理の弱さを深く理解しており、その感情の暴走を防ぐための「防波堤」として、自分自身で定めた厳格なルールを機械的に守り抜きます。
勝ち組が実践する資金管理ルールの例
- 投資上限ルール:「1レースあたりの上限金額は、総資金の2%まで」「1日の総投資額は●●円まで」といった、損失を限定的にするためのルール。
- 損切り(ストップロス)ルール:「1日の負け額が●●円に達したら、その日は潔くPCを閉じて競馬から離れる」という、傷口を広げないためのルール。
- 利食い(勝ち逃げ)ルール:「1日の利益が目標額の●●円に達したら、それ以上欲張らずにそこで終了する」という、得た利益を確実に守るためのルール。
これらのルールは、感情が入り込む余地のない、数学的な規律です。これを徹底することで、一時的な感情に流された無駄な敗北をなくし、長期的な視点での勝利を追求しているのです。
3. 合成オッズを常に意識する(リスク・リターンの最適化)
前述の通り、勝ち組は購入する馬券全体の期待払戻率である「合成オッズ」を常に意識し、トリガミを計画的に回避しています。しかし、彼らの意識は単なる「守り」にとどまりません。レースの性質に応じて、リスクとリターンのバランスを最適化するための「攻め」のツールとしても、合成オッズを活用しているのです。
例えば、「ここは1番人気が圧倒的で、堅い決着が濃厚だ」と判断したレースでは、あえて合成オッズを低めに設定し、トリガミにならないギリギリのラインで買い目を組み立て、少ないながらも確実な利益を狙います。一方で、「人気馬に不安要素があり、波乱の可能性がある」と読んだレースでは、意図的に人気薄の馬を多く組み入れて合成オッズを高めに設定し、的中した際の大きなリターンを追求します。このように、レースごとにリスク許容度を調整し、リターンを最大化する戦略的な思考が根付いています。
4. 感情を排し、結果を記録・分析する(PDCAサイクルの実践)
勝ち組は、大きなレースで負けても感情的に落ち込んだり、逆に大きな配当を手にしても驕り高ぶることはありません。彼らにとって、一つひとつのレース結果は、単なる勝ち負けではなく、自身の予想仮説を検証するための貴重な「データ」に他ならないからです。
そのために彼らが実践しているのが、自身の馬券購入の全記録とその分析です。これは、ビジネスの世界で言われるPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を競馬に応用する行為に他なりません。
- Plan(計画):レースを分析し、予想を立て、馬券を組み立てる。
- Do(実行):実際に馬券を購入し、レースを観戦する。
- Check(評価):レース後、なぜ的中したのか(しなかったのか)、予想のどこが正しく、どこが間違っていたのかを客観的に振り返る。
- Act(改善):その反省を次のレースの予想(Plan)に活かす。
この地道なサイクルを回し続けることで、自身の予想の癖や弱点を客観的に把握し、長期的に予想精度を高めていくのです。
このように、勝ち続けている人々は「当てたい」という短期的な射幸心を上手くコントロールし、期待値の高い馬券を、定められた規律の範囲内で買い続けるという、ある種の事業や投資に近い視点を持っています。そして、トリガミを計画的に避けるという行為は、これら全ての思考法を実践するための、具体的かつ重要な第一歩と言えるでしょう。
競馬で必ず儲かる買い方という考え方
- YUKINOSUKE
競馬を愛する多くのファンが、一度は心に思い描くであろう「必ず儲かる買い方」や「必勝法」。夢を壊すようで大変恐縮ですが、まず受け入れなければならない事実として、競馬において「これをやっていれば絶対に儲かる」という魔法のような方法は、残念ながらこの世に存在しません。しかし、そこで思考を止めてしまうのではなく、なぜ存在しないのかという仕組みを正しく理解し、その上で「どうすれば長期的にプラス収支を目指せるのか」という建設的な問いに移行することこそが、競馬との向き合い方を大きく変える第一歩となります。
なぜ「必勝法」は存在しないのか?
競馬に必勝法が存在しない理由は、そのゲームの根幹をなす「パリミュチュエル方式」と、そこに含まれる「控除率」という仕組みにあります。パリミュチュエル方式とは、ファンが投じた総額(売得金)から、主催者であるJRAや地方競馬団体が事業運営費として一定の手数料(控除率)を差し引き、残りの金額を的中者で分配する仕組みです。
これは、参加者同士がお金を奪い合うプレイヤー対プレイヤーのゲームではなく、必ず主催者(胴元)が手数料を取る構造になっていることを意味します。JRAが公式に発表している馬券種ごとの控除率は以下の通りです。
JRAが定める馬券種ごとの控除率
| 馬券の種類 | 控除率 | 参加者への払戻率 |
|---|---|---|
| 単勝・複勝 | 20% | 80% |
| 枠連・馬連・ワイド | 22.5% | 77.5% |
| 馬単・3連複 | 25% | 75% |
| 3連単 | 27.5% | 72.5% |
| WIN5 | 30% | 70% |
(出典:JRA公式サイト「馬券のルール」)
この表が示す通り、私たちが馬券を購入した瞬間、その金額の20%〜30%は手数料として差し引かれ、残りの70%〜80%のパイを的中者で分け合うことになります。つまり、参加者全員の回収率の平均は、理論上70%~80%程度に必ず収束するように設計されているのです。この大前提がある以上、100%勝ち続けることは数学的に不可能と言えます。
「儲ける」ための唯一の道筋:期待値を追うということ
しかし、「必ず儲かる」方法はないものの、この控除率の壁を乗り越えて回収率を100%以上に引き上げ、長期的なプラス収支を目指すための「考え方」は確かに存在します。それが、これまでの項でも触れてきた「期待値」をひたすら追い求めるという、極めて論理的なアプローチです。
期待値とは、ある馬券を無限に買い続けた場合に、1回の購入あたりでどれくらいのリターンが見込めるかを示す数学的な数値です。計算式は「オッズ × 本来の勝率(的中率)」で表されますが、ここで最も重要なのは「本来の勝率」は誰にも分からない未知の数値であるという点です。競馬の面白さと難しさは、この未知の勝率を、過去のデータやレース展開の分析を通じて、他の誰よりも正確に予測することにあります。
期待値の高い馬券を見つける思考プロセス
例えば、ある馬の単勝オッズが10.0倍だったとします。これは、世の中の多くのファンが「この馬が勝つ確率は10%程度だろう」と考えていることを意味します(1 ÷ 10.0倍 = 10%)。
しかし、あなたが様々なデータを分析した結果、「いや、この馬が持つ本来の能力や今回のレース条件を考慮すれば、勝率は20%はあるはずだ」と判断したとします。この時、この馬券の期待値は以下のようになります。
10.0倍(オッズ) × 20%(あなたが算出した勝率) = 2.0
この計算結果が「1」を上回る馬券こそが、「期待値が高い」馬券、すなわち「過小評価されているお買い得な馬券」です。このような馬券を買い続けることこそが、控除率のハンデを乗り越えてプラス収支を達成するための、唯一の合理的な道筋とされています。競馬で勝つとは、単に勝ち馬を当てることではなく、「オッズと本来の実力の間に生じた歪み」を見つけ出す知的なゲームなのです。
「必勝法」の誘惑とその危険性
期待値を追求する道は、地道な分析と検証を必要とする、決して楽なものではありません。だからこそ、多くの人が「簡単に儲かる」という甘い誘惑に惹かれてしまいます。インターネットやSNS上には「競馬必勝法」や「AIが導き出す絶対に儲かる情報」といった、魅力的な謳い文句で高額な情報商材や予想ツールを販売する業者も後を絶ちません。
科学的根拠のない情報に要注意
前述の通り、競馬の仕組み上、100%の確率で利益を保証する必勝法はありえません。そうした宣伝文句は、競馬の仕組みを理解していないか、あるいは理解した上で意図的に消費者を誤解させようとしているかのどちらかです。科学的根拠のない甘い言葉には決して惑わされないよう、強い意志を持つことが、あなたの大切な資産を守る上で何よりも重要です。
「必ず儲かる」という幻想を追い求めるのではなく、自分自身でレースを分析し、期待値を判断するスキルを地道に磨き上げ、トリガミという無駄な失点を避けながら回収率を高めていくこと。それこそが、競馬で真の「勝ち」を目指すための、遠回りのようで最も確実な王道なのです。
競馬のトリガミを理解して収支改善へ
- YUKINOSUKE
この記事では、多くの競馬ファンを悩ませる「トリガミ」という現象について、その言葉の基本的な意味から具体的な対策、さらには戦略的な付き合い方に至るまで、多角的な視点から深掘りして解説してきました。的中したにもかかわらず収支がマイナスになるという、一見不可解なこの現象。その背景には、単なる運や不運だけでなく、競馬というゲームが持つ構造的な仕組み、そして「当てたい」と願う人間ならではの心理が深く関わっていることをご理解いただけたのではないでしょうか。
主な原因である「買い目点数の増やしすぎ」や「人気サイドでの堅い決着」を理解することは、トリガミを回避するための第一歩です。しかし、私たちは同時に、すべてのトリガミが悪ではなく、高配当を狙う際の「保険」として機能する「良いトリガミ」も存在することを学びました。これは、投資資金の全損という最悪の事態を避けるための、高度なリスク管理術に他なりません。
そして、トリガミという無駄な失点を減らし、長期的な収支を改善していくための具体的な行動指針として、「買い目を絞る」「オッズをシミュレーションする」「資金を傾斜配分する」という3つの原則を紹介しました。単勝・複勝の1点買いという究極の守りの戦術から、フォーメーションを駆使して無駄を削る知的な戦術、さらには人気馬と穴馬を組み合わせて回収率の向上を目指す攻防一体の戦術まで、これらの原則を実践する方法は様々です。また、地方競馬特有のリスクや、見過ごすことのできない税金の問題といった、トリガミを取り巻く重要な関連知識についても確認しました。
最終的に、これらすべての知識とテクニックが指し示すのは、一つの結論です。競馬において「必ず儲かる買い方」という幻想を追い求めるのではなく、控除率という構造的な壁を乗り越えるために、「期待値の高い馬券」を自分自身の頭で考え、探し続けること。それこそが、長期的なプラス収支へと至る唯一の道筋なのです。
トリガミを正しく理解し、それを計画的にコントロールしようと努力するプロセスそのものが、あなたを感情的なギャンブルから脱却させ、知的で戦略的なゲームとして競馬と向き合う、新たなステージへと導いてくれるはずです。この記事が、あなたの競馬ライフをより豊かで、そして実りあるものへと変える一助となれば幸いです。
この記事の重要ポイントまとめ
- トリガミは馬券が的中しても購入金額より払戻金が少ない状態
- 語源は「粋(すい)が身を食う」ということわざが有力とされる
- 主な原因は的中を恐れて買い目点数を増やしすぎることにある
- オッズの低い人気馬同士の組み合わせでの的中も大きな原因の一つ
- 戦略的なリスクヘッジとして計画的に受け入れる「悪くないトリガミ」もある
- 投資資金の全損(不的中)を避ける保険としての役割を果たす
- 地方競馬は出走頭数が少なく中央競馬よりトリガミになりやすい
- トリガミによる払戻金も税法上は一時所得として課税対象になりうる
- ハズレ馬券は原則として経費に算入されないため注意が必要
- トリガミ防止の基本は「買い目を絞る」という選択と集中の原則
- 購入前にオッズを確認し払戻金をシミュレーションする習慣が大切
- 自信度や期待値に応じて投資金額に強弱をつける資金配分も有効
- トリガミに絶対にならない買い方は単勝や複勝の1点買い
- 多点買いではボックス買いよりフォーメーション買いが点数を抑えられる
- 長期的に勝っている人は目先の的中よりも回収率を最重視している
- 競馬の控除率の存在により「必ず儲かる買い方」は存在しない
- 期待値の高い馬券を見つけ出し買い続けることがプラス収支への道





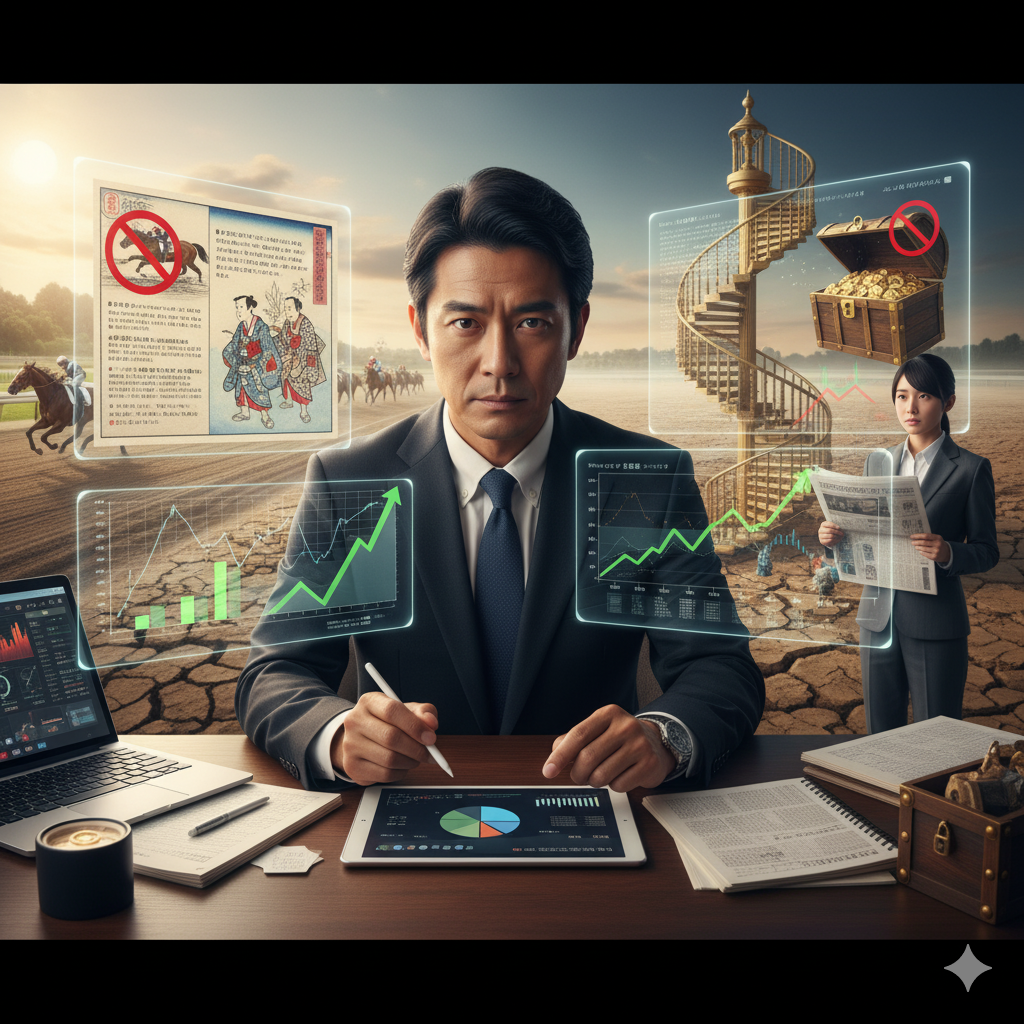



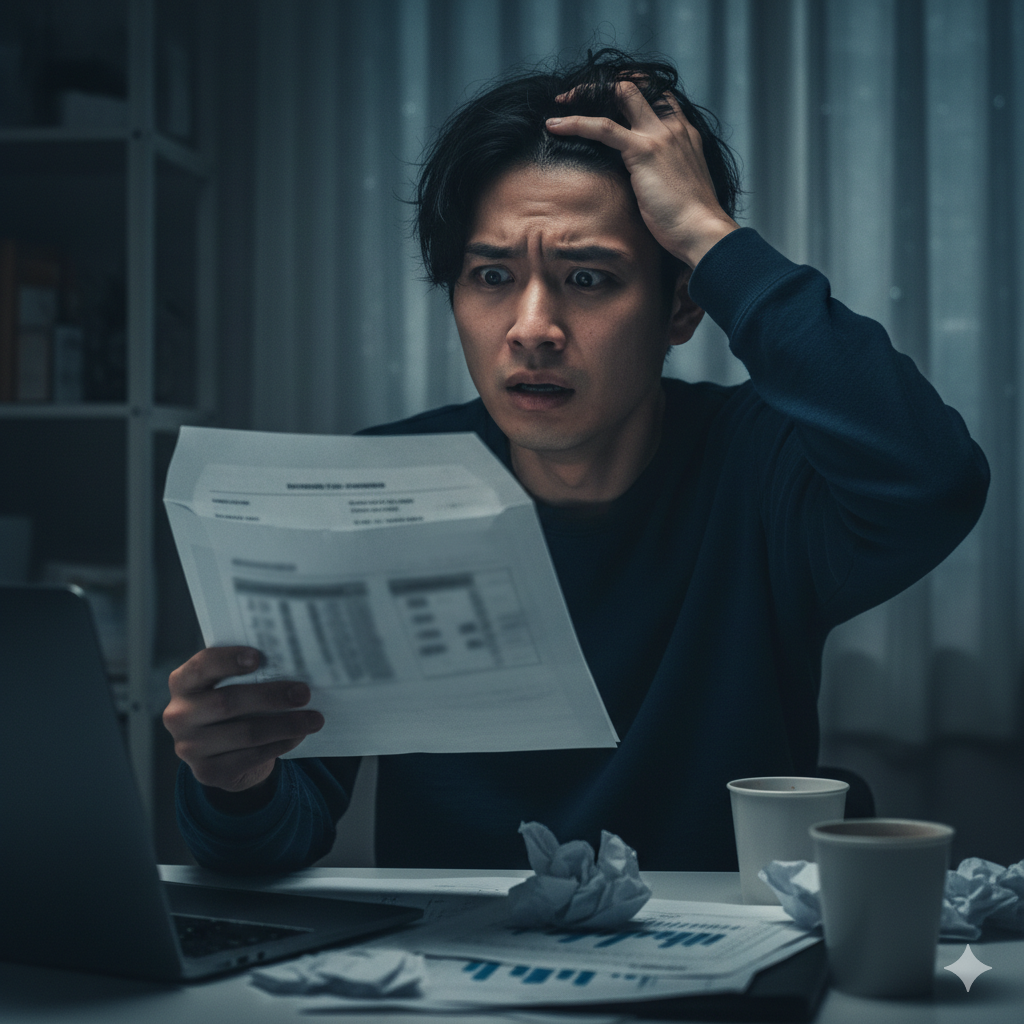





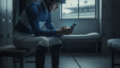
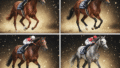
コメント